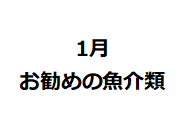
1月に旬を迎える魚介一覧

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

|
|

|

|

|
|
|
|

|

|

|

|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
シジミ(総称) |
|

|

|
|

|

|

|

|

|

|

ナマコ(総称) |
1月頃に旬を迎える魚をご紹介します。
また、おいしい食べ方も紹介するので、参考にしてみて下さい。
1月に迎える魚介とおすすめの食べ方
アイナメ
アイナメはの産卵期は、北日本で9月頃から、その他の地域では10月頃から始まり、翌年1月まで続きます。この時期になると大きなサイズが浅瀬に近寄るので、水揚げも増えます。身質が良いのは産卵期前の夏なのですが、水揚げが少なく小さいことから、アイナメと言うと冬のイメージが強いかも知れません。
産卵期を迎えると、オスの体表には婚姻色と呼ばれる金色に近い黄色が現れます。ただし、産卵後オスは飲まず食わずで卵が孵化するまで守るので、産卵後のものはさすがに避けた方が良いでしょう。

アイナメのおすすめの食べ方
産卵時期と被り、身が痩せている時期とは言え、大きなものが手に入る時期ですので、切身にして煮付けや唐揚げなどにするのがお勧めです。唐揚げは皮が付いたままにして、骨切りをするように細かく切れ込みを入れると味も染みやすく、また食べやすくなります。また、唐揚げはあんかけにしても美味しく頂けます。
もちろん、大きなものでまだ真子や白子を持ったままの状態であれば、お刺身にしても十分美味しいです。

ヨロイイタチウオ
見た目と名前からは想像できない非常に上品な白身魚です。昔は以西底引き船で大量に水揚げがあり、安価で美味しい白身魚として流通していましたが、外国漁船との漁場競合や、資源の減少により、今では滅多にお目にかかれない高級魚となってしまいました。小さなものは比較的まとまった水揚げが稀にありますが、鮮度保持が十分でない場合が多いので主に練り物の原料に向けられています。なので、小さなものを買われる際は鮮度確認が必須です。
大きなものは少しお高くなりますが、産卵を控えた早春頃から比較的水揚げが増えてきますので、見かけたらぜひ一度お召し上がり頂きたいお魚のひとつです。

ヨロイイタチウオのおすすめの食べ方
上品な甘みを持った白身ですが、少し水っぽいので、下処理で塩や昆布などで適度に水分を抜いた方が美味しくなります。鮮度が良いものであれば、下処理をしっかりした後に氷温で数日寝かせるとさらに旨味が増します。
濃い味付けにすると魚自体の旨味が感じにくくなりますので、煮物や焼物などにするばあいも控えめな味付けが良いでしょう。小さなものは皮や骨が付いたままブツ切りにして鍋や揚物にすると美味しく頂けます。

アンコウ(キアンコウ)
「西のトラフグ、東のアンコウ」と呼ばれるほど、冬の味覚の代表格のひとつです。アンコウは夏場を除いて水揚げがありますが、肝が大きくなるのは水温が低くなる12月から2月で鍋物需要と丁度重なります。
アンコウ(またはホンアンコウ)として流通していますが、吊るし切りにされるような大きなものは標準和名で言うキアンコウと言う種類で、標準和名のアンコウは大きくなっても40cm程度とされている上に、漁獲が少ないことや身質がキアンコウに若干劣るとされ、流通量は多くないようです(小さなものは区別されずに流通していることもあるようです)。

アンコウのおすすめの食べ方
アンコウは、「無駄のない魚」と言われており、身はもちろん肝、皮、胃袋、卵巣、エラ、ヒレまで食べることができます。これらは「アンコウの七つ道具」と呼ばれ、それぞれに独特の食感や味わいがあります。これらを余すことなく楽しむなら寒い冬にぴったりのアンコウ鍋ですが、非常にたんぱくな身質に加え水分が多いので、醤油、味噌などで少し濃いめの味付けにした方が良いとされています。身は唐揚げにしても美味しく頂けますが、下処理時に少し水分を抜いた方が旨味が増します。

コショウダイ
コショウダイはイサキの仲間で、イサキと同じく産卵期は夏です。産卵期には沿岸に集まって来るので、定置網などににかかりやすく漁獲量も増えるため見かける機会が増えますが、イサキと異なり産卵期の身質はかなり落ちます。また、イサキのように真子や白子を珍重するお魚ではないので(食べられないことはないですが、正直あまり美味しいものではありません)、産卵前後の秋から春先にかけての身が充実する時期が最も良いとされています。ただし、この時期は水揚げはあまりないので、お目にかかる機会は正直多くはありません。ただし、冬から春先に同じく旬を迎える魚の中には、たん白な白身魚や、脂がしっかりのった青魚も増えるためか、コショウダイ自体は水揚げが少なくても低価格で流通することが多いので、お財布にはとても優しいお魚になります。

コショウダイのおすすめの食べ方
イサキの仲間なので身質は良く似ていますが、若干旨味に欠けると評価もされることもあります。物足りなさを感じる場合は、生食の場合は昆布締めにしたり、カルパッチョなどのようにドレッシングをかけるなどしたり、加熱調理する場合は濃い目の味付けにしたり、出汁をいつもより多く加えるなど一工夫が必要です。
また、野締めなど下処理があまり良くないものは磯臭さが残ることもあるので、出来れば活締めのものを購入された方が良いでしょう。

ヒゲダイ
ヒゲダイはヒゲソリダイやセトダイと同じイサキ科ヒゲダイ属の一種です。名前の由来は下アゴにヒゲが密生している事に因んでもおり、これが大きな特徴となっています。
1年中水揚げがありますが、ヒゲダイやセトダイと同じく、まとまった水揚げが期待出来ないため、本種を目的とした漁はありません。水揚げが少ないため統計資料もなく、水揚げが多い産地も曖昧な超マイナーなお魚ですが、味の評価はかなり高いです。
暖海性のお魚のですので、季節による身質の変化もあまりないとも言われていますが、イサキとは異なり夏の産卵期に前後は避けた方が良いと言われています。

ヒゲダイのおすすめの食べ方
鮮度が良いものならもちろんお刺身がお勧めですが、ヒゲソリダイとは異なり皮は硬いので引いた方が良いでしょう。身には相当弾力があるので、薄切りにした方が良く、カルパッチョなどもお勧めです。
また、加熱もしても硬くなりにくい身質で、身離れも良いので、和洋中どのような料理にも合うとされています。

イトヨリダイ
タイと名前がついていますが、どちらかというとスズキに近い部類で、いわゆるあやかりダイのひとつです。
尾ビレの上葉が糸状に伸びており、これが泳いでいる時にひらひらと動き、糸を縒っているように見えることからが名前の由来と言われています。
癖のない上品な味わいの白身が特徴で、皮目も美しいため高級魚として扱われている地域もありますが、派手な見た目から逆に下魚扱いする地域もあるなど、両極端な扱いを受けています。
秋から初春に向けては、夏の産卵に備えて食性が高くなり脂がしっかりのってくる時期なので、見かけたら是非食べて頂きたいお魚のひとつです。

イトヨリダイのおすすめの食べ方
イトヨリダイは身に水分が多いのが特徴で、加熱しても柔らかく、フワフワの食感を楽しめます。ただし、お刺身にする場合は、昆布や塩などで水分を少し抜いて身を締めた方が美味しく頂けます。また、この時期は皮下に脂がしっかりのっていますので、どのような料理であっても皮は付けたまま調理することをお勧めします。

メダイ
1年中全国各地で水揚げがありますが、何故かメジャーな魚にならないお魚のひとつです。流通しているものの多くは50~60cmくらいですが、大きなものは1m程度にもなることに加え、歩留まりも良いお魚です。産地も伊豆半島沖から小笠原諸島、種子島や屋久島周辺など広く、鹿児島県ではプライドフィッシュにも指定されていますが、比較的深いところに生息しているため、水揚げが安定しないと言うのが欠点です。したがって、産地であってもスーパーなどに並ぶことはほとんどありません。
産卵期は冬なので、その前の夏から秋が旬となりそうですが、産地によって様々な説があり、三重県では春、鹿児島では1月から3月、山陰では7月から10月にかけてが美味しいとされています。

メダイのおすすめの食べ方
流通価格は安価な部類で、適度に脂が噛んだ白身はクセや臭みがなく、火を通しても硬くなりにくいなど、メジャーになっても良い要素ばかりですが、身質の個体差が激しいと指摘されるほど、当たり外れが多いお魚と言われています。なので、調理前に身質をしっかり確認して、それに見合った調理をすることをお勧めします。
脂が適度に噛んでおり、身に透明感がある場合は、どのような調理にも合いますが、身が白濁していたり、脂が少ない場合は、揚物やソテーなどに仕向けた方が無難でしょう。

ウルメイワシ
ウルメイワシの特徴は、潤んでいるように見える大きな目玉で、漢字では「潤目鰯」と書き、名前の由来にもなっています。マイワシに似ていますが、体表に斑点がないことから、マイワシと見分けることができます。
イワシの仲間は1年中漁獲されることから、季節感を感じにくいかもしれませんが、マイワシが夏に脂が乗るのに対し、ウルメイワシは秋から冬にかけて脂が乗ります。
小型が多く、傷みやすいという欠点もありますが、味はマイワシより良いという評価もあり、特に脂の乗りが少ない夏場のウルメイワシを使用したイリコや干物などに加工した場合は評価がグンと上がります。
残念ながら産地でもない限り、生鮮で良いものが出回ることは非常に少ない上に。春になると水揚げが少なくなり、ほぼ確実に加工に回されてしいます。脂ののりが良いこの時期は、少ないながらも生鮮で出回る機会が増えますので、見かけたらぜひお召し上がり頂きたいお魚のひとつです。

ウルメイワシのおすすめの食べ方
イワシ類は傷みが早い上、ウルメイワシは小型が多いため、干物やイリコなどに大半が加工されてしまいますが、それぞに独特の旨味があり、また1年中楽しむことも出来ます。
もちろん鮮度が良いものはお刺身ではもちろん、焼物、揚物、煮物、つみれなど何にしても美味しく頂くことが出来ます。

ウツボ
ウツボは暖かい海域であればどこでも生息していますが、食用にするのは四国太平洋側、紀州、伊豆諸島、長崎県、鹿児島県くらいで、特に和歌山県、高知県での消費が多いとされています。見た目もグロテスクで、漁師や釣り人の間では、網や仕掛けまで台無しにする嫌われ者ですが、味も栄養価も非常に良いお魚です。
産卵期は夏から初秋にかけてで、産卵期明けに食欲が旺盛になり身が太るため、冬の寒い時期が最も美味しいとされています。

ウツボのおすすめの食べ方
ウツボは、小骨が多い上に大小の骨が複雑に入り組んでいるため、それらを取り除くのが至難の業です。また皮のヌメリも非常に多いのも特徴で、下処理はハモ以上に面倒だと言われています。価格も安く、比較的入手しやすいお魚なのですが、こういったことが食用としてあまり広まらなかった理由だとも言われています。
下処理は非常に面倒なのですが、肉厚で柔らかな身は上質の鶏肉にも似たあっさり食感で、皮下のゼラチン質からはこってりとした濃厚な旨みがじゅわっと溢れ出します。
食用にする地域では、皮ごとタタキや湯引きなどにしたり、揚物、焼物、煮物など様々な料理で楽しまれています。

アオメエソ
標準和名のアオメエソより、流通名のメヒカリの方が恐らく馴染みがあるでしょう。この魚の最大の特徴は、流通名の由来にもなっている大きな目で、光を当てるとエメラルドグリーンに光ることです。厳密にはアオメエソとマルアオメエソの2種に分かれており、見た目はそっくりです。前者は静岡県以南、後者は千葉県以北に棲息しており、産地で区別することが出来ますが、味わいに大きな違いはないので、あまり気にする必要はないと思います。
福島県のいわき市では「いわき市の魚」に指定されており、福島県と宮崎県では「プライドフィッシュ」にもなっています。産地では非常に馴染み深いお魚ですが、深海魚であることなどから漁獲量は決して多いわけではなく、消費地に出回ることはあまりありません。
旬の時期は、千葉以北では主に冬から春とされており、南九州の日向灘では漁期が7月から翌年の4月(5月から6月は産卵のため禁漁)で、ピークは7月から8月の夏と、12月から1月の冬となっています。

アオメエソのおすすめの食べ方
大きさはキスくらいで、決して大きくはありませんが、クセがなく脂ののった白身で、旨味が強いお魚です。ただし、少し水っぽいところがありますので、調理前に少し水分を抜く下処理をしておくと良いでしょう。
鮮度が良いものであればお刺身がお勧めですが、鮮度落ちが早いので、とにかく手早く処理する必要があります。加えて小さなお魚ですので、骨を取り除くのにかなりの手間がかかりますが、それだけの手間をかける価値があるお魚です。
骨は柔らかいので、揚物にすると身と一緒に食べることも出来ます。そのほか、焼物、煮物などにしても美味しく頂くことが出来ます。

オニオコゼ
不細工な顔と背ビレの棘に強い毒を持つことで良く知られています。毒棘に刺されると激しい痛みと共に患部が腫れあがり、病院での手当てが必要となるので注意が必要です。
しかし、それでいてすこぶる美味しいことから高級魚として扱われており、特に活物は高級料理店での引合いが多く、かなりの値段で取引されています。
主な産地は三重県、瀬戸内海沿岸、九州などですが、近年は水揚げが減少していることもあり、各地で種苗養殖と放流が行われているほか、わずかですが養殖も行われています。
1年中水揚げがありますが、産卵期の5月から8月頃にかけて水揚げがかなり増えますでの、産地であれば比較的手ごろな値段でスーパーに並ぶこともあります。身が充実する時期は真冬から春先にかけてで、この頃は脂を蓄えて肝も大きくなりますので、年2回旬があると言った方が良いでしょう。

オニオコゼのおすすめの食べ方
調理に自信がない場合は、棘などを取り除いたものを購入しましょう。また、お刺身で食べるなら、出来るだけ活物か活〆されたものを選びましょう。
頭が大きい上、皮を引いても薄皮が残っているので、お刺身はにする場合は相当歩留まりが悪くなることを覚悟して下さい。ただ、そこまでする価値は十分にあります。
皮、胃袋、薄皮、肝は丁寧に洗って、湯引きすれば美味しく食べることが出来ます。アラは良い出汁が出ますので、お吸い物などにすると良いでしょう。小さなものは、2度揚げすれば頭から余さず食べることも出来ます。

カサゴ
カサゴは1年中見ることが出来るお魚で、旬には諸説あります。12月から2月頃までの冬から初春と言う説が一番多いようですが、初夏から冬と言う説もあり、また俳句の世界では春の季語となっていたりもしますので、本当にややこしいです。普通に考えると、産卵前の夏から秋が良いと言えますが、この時期は水揚げが少なくなる傾向にあります。ただ、いつ食べても大きく味が変わらないお魚のひとつですので、ここでは水揚げが比較的増える冬から春を旬として紹介します。

カサゴのおすすめの食べ方
カサゴに毒はありませんが、体中に鋭い棘が沢山ありますので、調理する際には注意して下さい。特に揚物にする際には、ヒレや棘は全て取り除いておきましょう。
大きくても20cm程度で、30cm以上になることは滅多になく、見ての通り頭が相当大きいので、特にお刺身にすると極端にか食部分が減ります。
ただしカサゴは、クセのない美味しい白身ですので、無理にお刺身にせずとも、焼物、煮物、揚物など、なんでも美味しく頂くことが出来ます。

メカジキ
メカジキ科に属する唯一の種で、カジキに中でも大型で、成魚になると全長5m、重さ400kgを超えます。他のカジキに比べて目が大きいことからメカジキという名前が付いたと言われています。
1年中水揚げされていますが、特に10月から翌3月に獲れるものは脂ののりがとてもよく、「冬メカ」とも呼ばれています。
国内では北海道から九州まで広く生息し、世界でも熱帯域から温帯域でも水揚げがあり、冷凍での出回りも比較的多いお魚ですが、スーパーなどに並ぶことは何故かほとんどありません。

メカジキのおすすめの食べ方
お目にかかる機会は少ないのですが、脂ののりが良いものを見かけたら、ぜひ味わってほしいお魚のひとつです。
皮も骨も外した切身や柵で流通しているので、調理は簡単です。鮮度が良いものが手に入ればお刺身も美味しいですが、加熱しても身が硬くなりにくいので、様々な料理にすることが出来ます。

スマ
カツオに良く似ていますが、胸鰭の下に複数の黒点があるのが特徴で、これがヤイト(お灸をすえた跡)のように見えることから「ヤイトガツオ」とも呼ばれています。
水揚げは1年中あると言われていますが、漁獲量はごくごくわずかのため、産地以外ではスーパーなどに並ぶことはまずありません。産地は鹿児島県、長崎県、三重県、和歌山県などの暖流域で、東日本にはほとんど見られませんので、馴染みのない方も多いお魚です。
1年を通して大きく身質が変化するころはありませんが、冬にはしっかりと脂がのるため、この時期を旬とする地域が多くあります。また、和歌山県や愛媛県では養殖も行われています。

スマのおすすめの食べ方
鮮度が良いものが手に入れば、お刺身やタタキがお勧めですが、寄生虫がいることもあるのでよく確認して下さい。
脂もしっかり乗っており、カツオより身が柔らかですので、揚物、煮物、焼物などの加熱調理をしても美味しく頂くことが出来ます。

アカガレイ
ヒラメのように大きな口をしていますが、カレイの仲間です。名前の由来は、裏表ともに全体に赤みがあり、特に腹の白い側や尾鰭の付け根辺りは血がにじんだように赤くなっていることからです。
主な産地の漁期は、北海道、福井県、京都府、鳥取県などで、福井県では「越前ガレイ」としてブランド化されています。
水揚げは1年中見られますが、産卵期に浅場に集まってくる2~3月は水揚げが増えます。また、身質は最も良いのは11~1月初めの産卵前前とされています。

アカガレイのおすすめの食べ方
1月下旬になると子持ちのものも目立ち始めますが、初めの頃は身が最も充実した時期ですので、鮮度が良いものが手に入ればお刺身がお勧めです。アカガレイは大振りなものの入手が可能ですので、肉厚で甘味たっぷりのお刺身を堪能することが出来ます。

イシガレイ
大きいものでは60cm程にもなる大型のカレイです。表も裏側も鱗がなく、表側の背や側線に沿って部分的に骨質状の硬い板があるのが特徴で、これが名前の由来にもなっています。
イシガレイとしての水揚げ統計がないため、産地などの詳細は不明ですが、ほぼ全国で水揚げが確認されており、昔から安くて美味しい惣菜魚として馴染みがあります。しかし、活物での流通が発達したため、その価値も高まり、活物や鮮度の良いものはそこそこの値段で取引されるようになりました。
イシガレイも夏に美味しいお魚のひとつで、お刺身で食べるなら夏から秋口辺りまでですが、夏場の水揚げは正直期待出来ず、それなりの値段になります。反面、秋から冬の産卵期には底曳網で大量に漁獲されることもあり、安価での出回りも期待出来ます。特に子持ちのものは煮付け用として古くから親しまれています。

イシガレイのおすすめの食べ方
各地で底曳網漁が盛漁期を迎えますので、水揚げも増えてきます。活物など鮮度が良いものの入手は困難になりますが、子持ちのものがお安く出回る季節ですので、真子や白子とともに煮付けにするのが最もお勧めです。

クロガレイ
クロガレイの主な産地は北海道で、クロガシラガレイに混じって漁獲されることが多く、また良く似ているため、区別することなくクロガレイまたはクロガシラガレイとして流通しています。ただし、割合的には圧倒的にクロガシラガレイの方が多くいようです。
クロガレイも他のカレイと同じように、腹に真子を持つ時期に多く漁獲され、真子ともども煮付けて美味しいお魚とされていますので、真子を持ち始める冬から春が旬となります。

クロガレイのおすすめの食べ方
臭みやクセは無く、透明感のある白身ですが、やや水分が多いため、身は柔らかめですのため、お刺身にする場合は、活物か活締めでないと厳しいかも知れません。また、子持ちになると身が薄くなるので抱卵前までの12~1月くらいまでのものが良いでしょう。
焼物も同様に水分を抜いたほうが良いとされていますが、煮物は身の柔らかさを活かすため、水分を抜く必要はありません。

ババガレイ
水揚げされたばかりのババガレイは粘液で体全体が覆われているため、見た目もあまり良くなく、名前の由来になっています。しかしその身は、クセがなく上品で、昔から煮付け向けの高級魚として扱われてきました。
主な産地は北海道太平洋側から東北の沖合にかけてで、八戸沖には大きな産卵場があります。産卵期は3月から4月で、腹に卵を持ったものは特に人気があります。
食べて美味しい旬の時期は脂がのる晩秋辺りから、腹に子を持ち、産卵してしまう前の初夏辺りまでと言われています。三陸地方では子持ちで縁起がいい「歳とり魚」として正月に食べる風習のある地域もあり、年末には非常に値が上がるそうです。

ババガレイのおすすめの食べ方
ババガレイの身は白身でクセが無く、甘みが強いのが特徴です。加熱調理しても身が硬く締まらずふわっとしたままなので、煮物を中心とした加熱調理用として人気が高い魚です。
鮮度が良いものは産地くらいでしかお目にかかれませんが、もし入手できたらお刺身もお勧めです。ただし、お刺身にする場合は、卵巣や精巣が充実する2月くらいまでのものが適当です。

マガレイ
名前に「マ」が付くように、カレイの中では最も広く親しまれているお魚と言っても良いでしょう。
主な産地は北海道、東北地方、北陸地方などで、12月になると底曳網漁が解禁となる地域も増えてきますので、まとまって水揚げされることが多くなります。ただし、資源の減少が進んでいることもあり、稚魚の放流も行われるようになりました。
マガレイは1年中どこかで水揚げされていますが、12~2月は身が最も充実する季節と言われています。加えて、底曳網シーズンと重なりますので、見かける機会もグンと増えます。

マガレイのおすすめの食べ方
鮮度が良く大きなものであれば、お刺身にも出来ますが、この時期は底曳網漁が主体ですので、良いものは入手しにくい時期です。
この時期は基本的に、大きなものは焼物か煮物、中小型は揚物などすると良いでしょう。

マコガレイ
マコガレイは全国各地で水揚げがあり、昔から食べられてきた非常にポピュラーなカレイですが、近年は資源の減少も見られるため、放流用の稚魚の生産も各地で行われています。
また、活物での流通が発達したことなどから、物によってはかなりの高値で取引されることもあります。
加えてブランド化も進められており、大分県別府湾の城下かれい、富山県射水市新湊の万葉かれいなどが特に有名で、いずれも活物で出荷されています。
昔は産卵のために浅瀬に集まってきたものを獲ることが主流だったため、冬から春先の産卵期を旬としていましたが、今では活物のお刺身の美味しさを求めるため、夏を旬とする地域もあります。

マコガレイのおすすめの食べ方
12~2月は底曳網漁のシーズンですので水揚げは増え、比較的安価で出回ります。加えて、子持ちのシーズンですので、まずは何と言っても煮付けがお勧めです。
未成熟の小さなものは二度揚げにすれば、頭から丸ごと食べることも出来ます。

マツカワガレイ
マツカワガレイの名前の由来は、鱗が硬く松の樹の表皮に見立てたからとされています。昔から美味しいカレイとして知られており、大きいものだと80cmにもなる大型のカレイです。しかし、現在100%天然と言えるものはほんの僅かで、ほとんどが稚魚放流によるものとされています。希少性が高いこともあり、超高級魚として流通しているため、一般に出回ることはなく、寿司店や割烹などの高級飲食店に卸されています。
主な産地は北海道で、ここでは資源保護のため全長35cm未満のものは海に戻す決まりがあります。また、北海道襟裳町から函館市南茅部にいたる海域で水揚げされたマツカワガレイはブランド化され、「王鰈(おうちょう)」として商標登録されています。
水揚げがわずかながら増えるのは産卵期で浅瀬に寄って来る晩秋から12月にかけてです。普通に考えると産卵前のものが良さそうですが、その時期のものは身が柔らかいとされ、敬遠されることが多いようです。

マツカワガレイのおすすめの食べ方
産卵期であっても、生食が基本のお魚ですので、活物か活〆されたものが前提です。お刺身やお寿司前提のお魚ですが、硬い鱗を除けばほぼ余すことなく食用可能です。
中骨やヒレなどの派生部位は揚物へ、アラや卵、肝などは煮付けにするととても美味しく頂くことが出来ます。

ムシガレイ
標準和名のムシガレイで呼ばれることはほとんどなく、ミズガレイとかミズクサガレイと呼ばれて流通しています。
産卵期の晩秋から春先にかけて、浅瀬に寄ってくることに加え、冬場は底曳網のシーズンに当たるため、水揚げは一気に増えます。産地では、美味しくて安い惣菜魚として人気があります。
全戸各地で水揚げが確認出来ますが、冬場に底引き網漁が盛んになる北陸から山陰地方、北九州から長崎にかけての日本海側で多く見居られます。

ムシガレイのおすすめの食べ方
鮮度抜群であっても、水分が非常に多い魚ですので正直お刺身には向きません。2月から3月は産卵前で最も身が充実している時期なので、煮付けが最も良いでしょう。
焼物や揚げ物などにする際は、塩などをして水分を抜いた方が、適度に身が締まり美味しく頂けますが、下処理が面倒な場合は干物を利用すると良いでしょう。

メイタガレイ
メイタガレイは全国各地で水揚げされており、非常に馴染み深いお魚のひとつです。名前の由来は諸説ありますが、全て特徴的な飛び出した目によるものです。
主な産地は北陸から山陰地方にかけてで、特に愛知県、三重県、和歌山県、瀬戸内海周辺地域などに多く見られます。大きくなっても30cm程度にしかならない小型のカレイですが、中部以西では美味しいカレイのひとつとして人気が高く、活物はかなりの高値で取引されます。
産卵期が晩秋から冬にかけてですので、身質が良いのは初夏から初秋までとされていますが、未成熟の小さいものは、冬になっても抱卵しないため美味しいとされています。

メイタガレイのおすすめの食べ方
この時期のものは基本的に真子か白子を持っているので、まずは煮付けがお勧めです。
未成熟の小さなものは煮付けはもちろんですが、焼物、揚物などにしても美味しく頂けます。

ヤナギムシガレイ
ヤナギムシガレイは、カレイの中でも水揚げが多い方なのですが、鮮魚での流通はあまりなく、もっぱら干物で流通しています。
味の良さには定評があり、干物であっても高価な部類に入ります。中でも冬場に獲れる30cm程度の大きなものは、高値で取引されています。
主な産地は、島根県、鳥取県、福井県、茨城県などです。福井県では「若狭がれい」としてブランド化されており、新潟県ではプライドフィッシュにもなっています。一方干物としての「笹がれい」は島根県産がよく知られています。
ヤナギムシガレイは底曳網漁主体で水揚げされますので、秋から春先が漁期となります。子持ちのものが好まれることと、漁期が産卵期に重なるため、旬は抱卵する11月頃から1月にかけてとなります。三陸などでは産卵期が多少ずれるようで、5月くらいまで水揚げが確認出来ます。

ヤナギムシガレイのおすすめの食べ方
身に厚みがないお魚ですので、出来るだけ大きなものを購入しましょう。
また、水気が多いので、お刺身にするには鮮度がすこぶる良いことが条件となり、これは産地でもかなり難しいです。
身は柔らかく、甘味があるので、焼物、煮物、揚物、蒸物などなんにでも合わせることが出来ますが、前述したように身が薄いので切身にせず、丸のまま調理した方が良いようです。
干物には一夜干しから上乾までありますが調理用途を考えると一夜干しが値段も含めてお勧めです。
小さなものは、鮮魚、干物に限らず二度揚げすると丸ごと食べることも出来ます。

ウマヅラハギ
ウマヅラハギは、カワハギ、ウスバハギと共に、カワハギの仲間では数少ない食用魚です。カワハギの仲間は鱗がありませんが、皮が非常に硬くザラザラしており、皮を剥いで料理するところからこの名が付いたと言われています。加えてウマヅラハギはその名前の通り、顔が馬に似ているところから来ています。
ウマヅラハギに限らず、食用となるカワハギは、水揚げが比較的多く、スーパーなどにもよく並ぶ惣菜魚ですが、淡白な白身は上品な味わいで、食感はフグに例えられることがあります。また、肝が非常に美味しいことでも知られています。
日本海側でよく獲れ、主な産地は、石川県、富山県、福岡県などです。
美味しい旬の時期は、産地により諸説あり、夏の産卵期を旬とする地域もありますが、この時期は単に水揚げが増えるだけで、決して身質が良いとは言えません。身が充実するのは産卵明けの晩夏から秋で、肝が大きくなるのは晩秋から春先にかけてなので、寒い時期が最も美味しいようです。

ウマヅラハギのおすすめの食べ方
ポピュラーな大衆魚ですが、活物や活〆されたものはお刺身用として高値で取引されることもあります。
鮮度の良いものが手に入れば、まずはお刺身がお勧めで、肝も一緒に頂くことが事が出来ますが、スーパーなどに皮を剥いで並んでいるものは、見た目が良くてもお刺身には向きませんので、注意して下さい。
肝が大きくなる冬場は何と言っても煮付け、鍋、汁物がお勧めで、あっさりした白身に肝を和えて食べると芳醇な旨味が口いっぱいに広がります。
小さなものは唐揚げにすると美味しく頂くことが出来ますが、骨はとても硬いので食用にはなりません。焼物にする場合は、身自体が非常にあっさりしていますので、味醂や味噌に漬けた方が良いようです。

カワハギ
カワハギは、ウマヅラハギ、ウスバハギと共に、カワハギの仲間では数少ない食用魚です。カワハギの仲間は鱗がありませんが、皮が非常に硬くザラザラしており、皮を剥いで料理するところからこの名が付いたと言われています。このお魚を単に「ハゲ」と呼ぶ地域が多いのですが、関西などでは単に「ハゲ」というとウマヅラハギを指すため、カワハギを「マルハゲ」と呼び区別しています。
日本各地に分布していますが、暖海系のお魚なので西日本の水揚げの方が多いです。また、静岡県や愛媛県などでは養殖も行われています。
カワハギは肝が美味しいため、一般的には肝が大きくなる秋から冬にかけてが旬と言われています。夏を旬とする説もありますが、これはカワハギ自体が1年を通して身質が大きく変わらない上に、夏場に美味しい白身魚が少ないことが要因のようです。

カワハギのおすすめの食べ方
比較的ポピュラーな大衆魚ですが、活物や活〆されポピュラーな大衆魚ですが、活物や活〆されたものはお刺身用として高値で取引されることもあります。
鮮度の良いものが手に入れば、まずはお刺身がお勧めで、肝も一緒に頂くことが事が出来ますが、スーパーなどに皮を剥いで並んでいるものは、見た目が良くてもお刺身には向きませんので、注意して下さい。
肝が大きくなる冬場は何と言っても煮付け、鍋、汁物がお勧めで、あっさりした白身に肝を和えて食べると芳醇な旨味が口いっぱいに広がります。
小さなものは唐揚げにすると美味しく頂くことが出来ますが、骨はとても硬いので食用にはなりません。焼物にする場合は、身自体が非常にあっさりしていますので、味醂や味噌に漬けた方が良いようです。

キチジ
標準和名はキチジですが、流通名の「キンキ」や「キンキン」で呼ばれていることの方が多いです。昔は捨てるほど獲れたと言われていますが、今では水揚げはほとんどなく、身質の良さからもっぱら超高値で流通するため、高級鮮魚店、百貨店、料亭などでしかお目にかかることが出来ません。特に釣物は評価が高く、さらに高値で取引されます。
このお魚は1年中、少ないながら水揚げがあう上、身質に大きな変化はないとされていますが、秋から冬に最も脂がのるようです。
近縁種にアラスカキチジと言うお魚がおり、冷凍魚としては超高値で流通しています。こちらもとても美味しいのですが、主に干物に加工されて流通していますので、調理用途が限られていしまいます。
国産の生鮮キチジは滅多にお目にかかれるものではありませんので、機会があればぜひ一度はお召し上がり頂きたいお魚のひとつです。

キチジのおすすめの食べ方
キチジと言うと、甘辛い煮付け、塩焼などを思い浮かべる方も多いと思います。もちろん加熱しても美味しいことに間違いはないのですが、鮮度の良いものが手に入れば、まずはお刺身がお勧めです。獲れたてでもその身は柔らかで、皮も柔らかく、皮下に脂と旨味が詰まっているので、皮は引かずに湯霜造りか炙りにするのがお勧めです。また、身の旨味もたっぷりなので、塩や昆布で水分を抜いたり、旨味を足すなどの手間も特に必要ありません。

キビナゴ
キビナゴは、スマートな体は美しい銀色で、中央には鮮やかな青色の帯模様が走っています。その見た目から、「帯(きび)」の「小魚(なご)」と名付けられたと言われています。
大きくなっても10cm程度と、ニシンの仲間の中では最も小さな部類ですので、捌くのに一苦労しますが、産地ではとても人気の高いお魚です。
キビナゴは、九州、四国太平洋側、紀州、中部などに見られますが、特に鹿児島県、高知県、長崎県が多く、中でも鹿児島県では郷土料理になっています。
身が締り美味しくなるのは12~2月頃の寒い時期とされていますが、産卵期を迎える春から初夏頃にかけては海岸近くに産卵のために寄って来るので水揚げが増えるため、12~6月まで旬が続くと言っても良いでしょう。
また、キビナゴは小さいこともあり鮮度落ちが早いので、干物に加工されたものも多く流通しています。

キビナゴのおすすめの食べ方
この時期は走りでかなり小さく、捌くのに相当の労力を必要としますが、身が最も充実している時期ですので、まずはお刺身がお勧めです。お刺身は普通刺身醤油で頂くのですが、キビナゴは酢味噌との相性が抜群と言われています。
鹿児島県では手開きしたキビナゴを菊の花にかたどって並べる「菊花造り」が有名で、冷凍加工品も一般に流通しています。

キュウリウオ
キュウリウオの名前の由来は、キュウリのような香りがすることからと言われています。シシャモやワカサギの仲間で、シシャモに似ているところもあるので、小さなものは間違ってシシャモとして販売されていることもあるそうです。しかし、国産のシシャモは超高級魚なのに対し、キュウリウオは大衆魚なので、間違えたでは済まなそうなものですが…。また、さらに小さなものはワカサギとして売られていることもあるそうですが、ワカサギとの見分けは簡単なので、こちらは単に選別するのが面倒だからかも知れません。
キュウリウオは冷水域のお魚で、国内の産地は北海道だけです。2歳くらいになると、4月下旬から5月下旬にサケのように河を遡り産卵しますが、サケとは異なりその場で息絶えることなく(個体差はありますが)産卵後は海に戻ります。またサケのように大きな回遊はせず、産卵場所近辺で普段も生活していますので、水揚げは1年中確認出来ます。ただし、身質が最も良いのは産卵前の冬から春先とされています。

キュウリウオのおすすめの食べ方
鮮度の良いものは、もちろんお刺身でも食べられますが、香りを嫌う人もいるようです。また、アニサキスがいることもあるので、基本的に焼物、煮物、揚物などの加熱調理がお勧めです。
干物も流通しており、こちらも焼物、煮物、揚物に利用できますが、頭や骨はしっかりしているので、シシャモやワカサギのように頭から丸かじりは止めておいた方が良いでしょう。

チカ
チカは主産地である北海道では水揚げも多く、安価で流通していることもあり、知名度100%と言っても過言ではありません。しかし、その他の地域では、水揚げ自体が少ないことなどから知名度はかなり低く、良く似たワカサギと区別なく流通していることもあるようです。
チカは大きくなると20cm程度となり、ワカサギより一回り大きくなります。またワカサギは海淡水両方に棲むことが出来ますが、チカは海水のみしか棲息出来ません。
春に産卵期となるため、秋から冬はそれに向けて栄養を蓄える時期ですので、よく太ったものが手に入りやすくなります。

チカのおすすめの食べ方
チカの身は柔らかく、淡白な味わいの白身です。ワカサギより大きいので、鮮度が良ければお刺身にも出来るそうですが、アニサキスが寄生していることもあるので、基本的には焼物、揚物、煮物などの加熱調理がお勧めです。
揚物にする場合は、小さなものであれば物骨も柔らかく気になりませんが、大きなものしっかり取り除いておいた方がよいでしょう。
煮物にする場合は、甘露煮のようにじっくりと味を沁みこまた方が良いとされています。

ワカサギ
ワカサギの主な産地は青森県、北海道、茨城県、秋田県などの北日本で、水揚げの最盛期は産卵を控えた冬から春先です。凍結した湖の一部に穴をあけて釣り糸を垂らす「穴釣り」は冬の風物にもなっているため、寒いところのお魚、冬のお魚と言うイメージを持たれる方も多いとは思いますが、実ははほぼ1年中安定したた水揚げがあります。また、北陸や山陰でもわずかながら水揚げがあります。
前述したように湖での釣りがイメージとしてありますので、淡水魚と思われる方も多いのですが、実ははアユと同じように河川と海を行き来する両側回遊型と、一生を淡水で過ごす陸封型がいます。また、同じ水域で生活していても両側回遊型と陸封型が混在することもありますので、獲れる場所は湖だけではなく、河川、汽水域、海岸など実に様々です。
産卵期は地域差があるため、1~5月と幅があります。ざっくり言うと11~12月頃は産卵前の身が充実したもの、1~5月は抱卵したものが美味しいとされていますが、小さなお魚ですので、そこまで違いを感じることは難しいため、実際には1年を通して美味しく頂くことが出来ると言っても良いでしょう。

ワカサギのおすすめの食べ方
非常に小さなお魚で、頭も骨も柔らかく丸ごと食べることが出来ます。ただし、釣物には口の中や胃袋に未消化の餌が残っていることもありますので、面倒でも必ずチェックして下さい。残ったままだと食味が悪くなりますので、必要に応じて頭や内臓を除去するなどした方が良いでしょう。
調理法としては正直何でもござれですが、人気が高いのは天ぷらや唐揚げなどの揚物です。煮物にする場合は甘露煮がお勧めです。また、抱卵の有無によって調理法を変える必要も特にありません。

キンメダイ
キンメダイは、とても鮮やかな赤色と金色の目が特徴で一際目を引きます。名前の由来もこのキラキラした金色の目からです。
主な産地は静岡県、神奈川県、千葉県、東京都、高知県などですあるようで、産地ではブランド化も進められており、
静岡県伊豆地方 須崎の日戻り地金目・稲取キンメ・伊東の地キンメ
千葉県房総地方 銚子つりきんめ・外房つりきんめ鯛
高知県室戸地方 土佐沖どれキンメダイ
などが有名です。
キンメダイの産卵期は6~10月頃にかけてで、この時期に水揚げが増えるところもあるため、夏を旬とする地域もありますが、最も美味しい旬の時期は12~2月にかけてとされています。また、赤いお魚は縁起が良いとされる風潮からか、特に年末年始は縁起物として高値で取引されることが多くなります。
ちなみに、近縁種にはフウセンキンメやナンヨウキンメなどがおり、日本近海でも水揚げが確認出来ます。いずれも食味がそこまで変わらないと評価されているため、大半はキンメダイとして流通しています。

キンメダイのおすすめの食べ方
キンメダイは身が非常に柔らかいため、昔はお刺身には向かないとされていましたが、漁法や流通の発達により、身が締まった良いものが入手できるよになったため、今ではお刺身で食べるのが当たり前になっています。お刺身にする場合、皮は赤くて見た目も良いことに加え、たっぷりと脂を含んでいるため、湯霜や焼霜にして一緒に食べる方が良いでしょう。
あっさりした味わいを求めるなら焼物も良いですが、キンメダイといえばやはり煮物です。脂ののったホロホロの白身は、少し濃い味付けにするのが定番です。

シログチ
シログチは標準和名で呼べれることはほぼなく、単にグチと呼ばれたり、大きな耳石を持っていることからイシモチと呼ばれたりすることの方が多いお魚です。釣りをされる方であれば、投げ釣りや船釣りなどでよくお目にかかるため馴染みもあるでしょうが、鮮魚として一般に流通することはほとんどありませんので、一般的には馴染みがほとんどないお魚です。その理由としては、水分が多く見が柔らかい上、鮮度落ちが早いなどと言われています。ただし、昔から蒲鉾原料としては引き合いが強いため、大半がすり身に加工されています。シログチはイトヨリダイと同じく、すり身は評価が非常に高く、これを使った練り製品は高級品として流通しています。
産卵期は夏で、浅瀬に寄って来るため水揚げは増えますが、身質は決して良いとは言えないことに加え、鮮魚としての評価が低いため、扱いも雑になりますので、良いものの入手は自分で釣りでもしない限り困難です。身質が最も良いのは冬とされていますが、水揚げは少ないので、これまた釣りでもしない限りこの時期のシログチの入手は難しいでしょう。

シログチのおすすめの食べ方
この時期のシログチは適度に脂がのり、甘味も増していますので、お刺身にすると美味しく頂くことが出来ます。身が柔らかい感じる場合は、下処理の際に塩などで少し水分を抜くと良いでしょう。
お刺身にするのが厳しい場合は、煮物、焼物、揚物などにすると美味しく頂くことが出来ます。

ウグイ
ウグイはコイ目に分類される日本の在来種で、沖縄県を除く日本全国に分布しています。河川、ダム湖を含む湖など淡水域はもちろんのこと、海に下るタイプもいるため、汽水域や海水域でも生息が確認されています。ウグイの名前の由来は鵜に良く食べられるところからきているそうです。また、オイカワなど他のコイ科の細長い魚とひとまとめにされハヤと呼ばれることもあります。
広く分布していることもあり、存在自体はとてもポピュラーお魚なのですが、食用としての知名度は今ひとつです。ウグイは汚染された水域でも生息出来るため、泥臭さや、コイ科特有の小骨の多さが原因で「不味い魚」と評価されてしまうことが多いことが理由のようです。ただし、水質が良いところで獲れたものは普通に美味しく、長野県、栃木県、富山県の一部では郷土料理として提供しているお店もあります。
ウグイの旬は産卵期前の初冬から春とされています。産卵期を迎えると、雌雄ともに鮮やかな3本の朱色の条線が走る婚姻色へ体の色が変わりますので、状態を見極める目安になるでしょう。

ウグイのおすすめの食べ方
ウグイの旬は、初冬から初夏の時期までと言われています。特に寒い時期は「寒バヤ(かんばや)」と呼ばれており、脂がのってとても美味と評されています。
塩焼きはもちろん、洗い、田楽、唐揚げ、天ぷらなど、様々な川魚料理で楽しむことが出来ます。
大きなものは小骨の多さが気になりますので、料理によっては骨切りなどの処理をして下さい。
※寄生虫がいる場合がありますので、洗いなど生食する場合は、除去を徹底するか、冷凍処理して寄生虫を死滅さえたものを使いましょう。

コイ
国内には日本在来種のノゴイと、ユーラシア大陸からもたらされて今では普通に見られるコイの2種がいます。ノゴイは希少種なので、もっぱら食用とされているのはコイの方です。内臓や生殖巣も食用とすることもあるため、これらが大きくなり脂がのって来る冬が旬と言われています。
コイは身近な水源で飼うことが出来る上、雑食性で成長が早いため、特に海から遠い山間部では人気の高いお魚でしたが、流通の発達から海水魚が簡単に入手出来るようになったため、今では特種な食べ物になりました。取り扱っている店もどんどん減っているため、前もって注文しておかないと食べることは難しくなっています。当然需要は大きく減少し、これに伴い値段も下がったため、生産者も非常に少なくなっています。また、現在流通しているものの大半は養殖で、天然物はまずありません。
産地としては、秋田県、山形県、福島県、群馬県、滋賀県、宮崎県、福岡県、長野県、富山県、鹿児島県などがあげられますが、産地で消費する量もごくわずかです。郷土食として残っている地域もありますが、年に数回食べるか食べないかになっているようです。

コイのおすすめの食べ方
養殖であっても、食べる前にはきれいな水で数日間は餌を与えずに飼って、胃の内容物吐き出せるなどして臭みの元を出来るだけ取り除く必要があります。鱗はよく加熱すると柔らかくなって食べられないことはないのですが、これは好き好きです。
血合いの赤い透明感のある白身で、ゼラチン質が多いため、加熱してもトロッとしており、固くはなりません。また、身よりも卵巣、精巣、内臓を好む場合もあるため、コイコクや煮付けにはもっぱら内臓が充実したものを使います。
コイと言うと洗いが有名ですが、これは夏の料理で、脂がのったこの時期のものは適さないようです。
※天然のコイには寄生虫がほぼ確実にいますので、生食は絶対にしないで下さい。生食する場合は必ず養殖のものを使いましょう。

メゴチ(総称)
標準和名でメゴチと言うお魚はいますが、食用として出回ることはまずありません。ここで言うメゴチはネズッポ科魚種の総称で、セトヌメリ、ヌメリゴチ、ネズミゴチなどを区別せずに言う場合を指します。
メゴチ(総称)はほぼ全国で水揚げされますが、網にかかると棘が絡んで外しにくいなど嫌われることが多いお魚で、水揚げされても非常に雑な扱いを受けることも多く、さらに釣りの外道としても有名です。加えて、小さくてヌメリが多いため、非常に捌きにくいことと、鮮度落ちもすさまじく早いので、処理を怠るとすぐに臭みが出るなど、嫌われる理由が満載です。しかし、その身は上品で甘味が強く、火を通しても硬くならないので、特に天ぷらのタネとしては価値が高いです。ただし、スーパーなどに並ぶことはまずないので、食べたい場合は、自分で釣るか、常日頃から取り扱いのある天ぷら専門店などに行かねばならないでしょう。
夏に産卵期を迎えるため、春先から食性が上がり身が肥えることに加え、水揚げが増えるため、春から夏を旬とするところが多いのですが、味が良いのは冬から春とされています。

メゴチのおすすめの食べ方
鮮度が悪いとヌメリがひどくなり、身にも臭いが移るので、とにかく鮮度が命です。
お刺身に出来ないこともないですが、難易度がかなり高いので、素直に天ぷらなどの揚物で頂くのが良いでしょう。

タイセイヨウサケ
名前の通り、大西洋の北部冷水域に生息しているサケで、アトランティックサーモンと呼ばれ、以前は北米北欧の大西洋沿岸地域のみで消費されていました。1980年代からノルウェーで盛んに養殖されるようになり、その後、需要の高まりとともに、南半球のチリ、ペルー、オーストラリアのタスマニア島などでも養殖が始まりした。元々大きな需要があったことに加え、流通の発達により販路は世界中に広がり、現在では生鮮での空輸も増えています。世界中で消費されているるサケの中で最も需要が高く、ほぼ養殖で賄われています。日本国内でもサーモンと言うと、ほとんどがタイセイヨウサケを指します。また、他の養殖魚と比べて、骨取りフィーレやロインなどの加工品の割合が非常に多く、捌く手間などが大きく軽減されているのも、需要が拡大するひとつの要因でしょう。また、特に北欧、豪州では厳格な管理の元で養殖されているため、身質も非常に安定しており、1年中良質のお魚を口にすることが出来ます。
また、サケの中でも大型で、大きなものでは1ⅿを超えることもある上、体に比べて頭が小さく、歩留まりが良いのも特徴のひとつです。

タイセイヨウサケのおすすめの食べ方
養殖は寄生虫の心配がありませんので、ほとんどが生食用として流通しています。日本国内ではお刺身やスシネタとしての需要が定着しており、スーパーや寿司店には必ずあると言っても良いお魚になっています。
脂が多く、身が柔らかいので、加熱調理しても身が硬くなりにくいのも利点で、生食に限らず色々な料理を楽しむことが出来ます。ただし、脂が非常に多いので、お好み次第で、塩焼きなど幾分脂を落とすような調理や、ポン酢などあっさりとした調味料などと合わせる工夫も必要になるでしょう。

コノシロ
コノシロは大きさで呼び名が変わり、5cm位までの稚魚をシンコ、10cm位迄をコハダ、13cm位をナカズミ、それ以上をコノシロと呼び流通しており、冬は一番大きなコノシロサイズの水揚げが増えます。ただし、他のお魚と同様に明確な基準があるわけではないので、その時々で呼び名は微妙に変化します。
コノシロが、鱗が多くて取りにくい、身が薄い、小骨が多い、焼くと嫌な臭いがするなど、あまり良い条件が揃わないため、積極的に食用に向けない地域もありますが、冬は脂がのりとても美味しいシーズンとされています。特に江戸前寿司では大きなものは全てコハダと呼び、光物のネタとしてはなくてはならないもののひとつになっています。
コノシロの水揚げは全体で5000トン程度と水産物としては決して多くはありません。そのうち千葉県が全体の40%を占めていますが、これは最大の消費地である東京が近いためと考えられます。

コノシロのおすすめの食べ方
あまり知られてはいませんが、コノシロは出世魚としての縁起を担ぎ正月料理に用いられることもあります。クチナシで黄色に染めた粟と漬けて「五穀豊穣」を願います。

ニシン
ニシンは産地がほぼ北海道に限られるため、未だに生鮮での出回りは北海道近辺に限られており、ニシンそのものより数の子や身欠きニシンなどの加工品の方が知られています。
春先に産卵のために北海道沿岸に現れるため、産地では「春告魚」と呼ばれています。明治末期から大正期の最盛期には北海道で100万トンくらい獲れた記録が残っていますが、今では5000トン程度に留まっています。
産卵期は5月位まで続きますが、最も良い時期は3月位までとされています。ただしオホーツク海側の一部では流氷の影響で漁が出来ない時があったりしますので、同じ北海道でも海域により漁期にずれが生じます。

ニシンのおすすめの食べ方
産地でないとかなり難しいですが、鮮度が良いものが手に入ればお刺身がお勧めです。産卵期であっても身にはしっかり脂がのっているのがニシンの特徴でもあります。しかし、小骨が非常に多いお魚ですので、特にお刺身にする場合には、しっかりと取り除く必要があります。
他の料理も同様に骨を取り除いておくと食べやすくなりますが、細かく骨切りしておいても良いでしょう。

マサバ
マサバは大きく分けて、回遊型と瀬付き型に分かれています。回遊型は、太平洋の黒潮の内側を回遊するもの、日本海沿岸を回遊するもの、東シナ海を回遊するものの3グループに分かれており、それぞれ夏季に北上し秋から冬にかけて南下し、特に南下し始めのものは餌をたっぷり食べていることから、脂ののりも良く美味しいとされています。
一方瀬付きのものは各地でブランド化されており、関サバ(大分県佐賀関)、金華サバ(宮城県石巻)、松輪サバ(神奈川県三浦)などが有名で、これらは餌を求めて回遊することもないので、身質は1年を通して比較的安定していると言われています。
水揚げは年間通しての統計しかありませんが、茨城県、長崎県、静岡県などが多いようですが、特にどこのものが良いと言うわけではなく、美味しいとされる秋冬に水揚げがある地域であれば問題ないでしょう。場所によっては、夏に水揚げが増えるため、夏を旬とするところもあるようですが、マサバの産卵期は3~6月で、産卵期と産卵期明けは食性も落ちて身も痩せているので、あまり良い評価は出来ません

マサバのおすすめの食べ方
瀬付きのものは比較的安心とされていますが、サバの類は基本的にアニサキスが寄生していることが多いので、生鮮の生食は控え手下さい。どうしてもの場合は、必ず-20℃以下で24時間以上冷凍したものを使いましょう。
秋から冬は、どこのものであっても脂がしっかりのっているので、どのような料理にも合います。脂が少ない小さなものはソテーや揚物など、油分を足す調理をすれば良いでしょう。
※サバにはヒスチジンという成分が含まれており、鮮度が落ちて古くなるとヒスタミンというアレルギーを起こす成分に変化しますので、鮮度が良いうちに食べ切るか、余った場合は冷蔵ではなく冷凍することをお勧めします。。

サヨリ
サヨリは、冬に生まれた当歳魚が春先に海岸近くに集まることが多く、見かける機会が増えるため「春告魚」と呼ばれることもありますが、実際には1年中どこかで水揚げがあります。
産地としては、関東では東京湾周辺、北陸から山陰の日本海沿岸、瀬戸内海沿岸などが知られていますが、突出したところはなく、水揚げは決して多くありません。
小さいものは捌くのが大変なので干物などに加工されることが多いようです。逆に大きなものは料理屋や寿司屋などの引合いが強く、高価で取引されるため、スーパーなどに並ぶことはほとんどありません。名前は知っていても、意外とお目にかかる機会は少ないお魚です。
盛漁期は地域により多少ズレがありますが、夏に生まれたものが沿岸近くに寄って来る晩秋から、これらが成長する春先までとするところが多く、これは美味しいとされる旬とも重なります。
産卵期と産卵期明けに当たる夏から初秋は、身が細いお魚がさらに痩せてしまうため、お勧めは出来ません。

サヨリのおすすめの食べ方
まだまだ小さいものが多い時期ですが、少し大きめの物もチラホラ混じり始めますので、そう言うものが手に入ればお刺身がお勧めです。
中サイズは開いて天ぷらにしたり、煮物や焼物にすれば美味しく頂くことが出来ます。

サワラ
サワラも大きさで呼び名が変わるお魚のひとつです。地域により多少違いはありますが、40cm以下のものをサゴシ、50cmを超えたくらいからヤナギ、70cm以上をサワラと言います。ただし、他のお魚同様、その時々で基準が変わりますので、名前だけで大きさを判断することは出来ません。
また、サワラは地域により旬とされる時期が異なります。サワラは漢字で「魚へんに春」と書きますので、春の魚と言うのが通説で、俳句でも晩春の季語になっています。これはサワラが4~5月頃に産卵のため瀬戸内海などに集まり、沢山獲れることから来ています。春は身だけではなく、真子や白子も一緒に楽しむことが出来ます。この時期の産地としては、高知県、和歌山県、岡山県などが有名です。
脂ののりも良く身が最も充実している時期は産卵前の冬で、関東では寒鰆と呼ばれており、東京湾周辺の海域で水揚げが確認されます。ただし、実際に水揚げが多いのは福井県、石川県、京都府などの日本海沿岸で、質の良いものは産地であり消費地でもある岡山県などへも送られています。

サワラのおすすめの食べ方
冬は産卵に備え、タップリ栄養を蓄える時期ですので、身がとても充実しています。鮮度が良く、大きなものが手に入ればまずはお刺身がお勧めですが、皮下の脂も美味しいので、皮は引かずに焼霜造りにすると良いでしょう。ただ、身が割れやすい魚ですので、出来るだけ丁寧な扱いがされているものを選びましょう。
もちろん、焼物、煮物などにしても美味しく頂くことが出来ます。

アカシタビラメ
シタビラメは、カレイ目ウシノシタ科に属するお魚の総称で、その形が舌に似ていることから、漢字で「舌平目」と書きます。日本国内で食用として流通しているものには、アカシタビラメ、オオシタビラメ、クロウシノシタ、イヌノシタなどがいますが見た目で似たようなものは区別されずに流通することが多いです。アカシタビラメもよく似たイヌノシタと区別されずに、アカシタとして流通しています。
アカシタビラメの産卵期は主に夏で、早いところでは3~5月ですので、産卵期前の冬から梅雨時くらいまでのものが身質が良いとされています。しかし、産卵明け以外は身質がそう大きく変わるお魚ではないため、水揚げが増える夏の産卵期を旬とする地域もあります。
主な産地は、香川県、徳島県、愛媛県、大阪府、岡山県など瀬戸内海沿岸で、これらの地域では普段からスーパーなどにも並びます。

アカシタビラメのおすすめの食べ方
アカシタビラメに限らず、シタビラメの仲間は相当大きなものでもない限り身が薄いので、お刺身にする場合は、相当の技術が必要な上、歩留まりもかなり悪くなります。また、身自体は甘味があって美味しいのですが、水分が非常に多く柔らかいので、これを適度に抜く強いた処理も必要となります。難易度は高いのですが、旬の時期に良いものが手に入ったら試してみる価値はあります。
ソテー、ムニエル、煮付けにするのが一般的ですが、小さなものであれば、しっかり揚げれば頭から食べることも出来ます。ただし、焼物にする場合は、お刺身と同様に少し水分を抜いた方が良いでしょう。

シラウオ
シラウオがスーパーなどに並ぶことはなく、ほとんどが料理屋直行となるため、名前を聞いたことがあっても実際にはお目にかかる機会が少ないお魚です。北海道から九州沿岸までと広い範囲で水揚げがあり、島根県の宍道湖では「宍道湖七珍」のひとつとして有名ですが、その量自体が少ないためか、地元の人であってもあまり口にする機会はありません。
シラウオは1年魚で産卵を終えると死に絶えてしまうことに加え、産卵期のため川を遡上する2~4月がを逃すと、来年までお目にかかることが出来ません。また、立春以降に水揚げが増えるため春告魚のひとつとしても有名です。ただし、北海道の網走湖では、春に湖内で生まれ育ち、秋に越冬するために川を下り海へ向かう際の9~10月を漁期としています。
また、シラウオは同じ時期に旬を迎えるシロウオと混同されやすいのですが、シラウオはシラウオ科で、背びれと尾びれの間に脂びれがあり頭が尖っているのに対し、シロウオはハゼ科で頭が丸く全体に黄色味を帯びているので、名前は似ていますが、見ればすぐにわかります。

シラウオのおすすめの食べ方
鮨ネタにも使われるなど生食されることも多いのですが、稀に横川吸虫や顎口虫が寄生していることがありますので、生食する場合は-20℃以下で24時間以上冷凍して下さい。
小さい体に似合わず旨味の強いお魚ですので、加熱しても美味しく頂くことが出来ます。お勧めは、天ぷら、唐揚げ、佃煮、お吸い物などですが、すぐに火が通ってしまうので、加熱し過ぎないように注意して下さい。
 ※農林水産省HP参照
※農林水産省HP参照
シロウオ
シロウオがスーパーなどに並ぶことはなく、ほとんどが料理屋直行となるため、名前を聞いたことがあってもお目にかかる機会が少ないお魚です。北海道から九州までの広い範囲で水揚げがあり、産卵期を迎える早春から海から川に遡上します。この時期は地域により多少ずれがありますが、おおむね2月中旬~4月上旬が最盛期とされています。シロウオは生きている状態では黄色みを帯びた透明で、腹側に黒い点)がありますが、死んでしまうと白くなります。また加熱調理しても白くなることから、これが名前の由来とされています。
また、シロウオは同じ時期に旬を迎えるシラウオと混同されやすいのですが、シロウオはハゼ科で頭が丸く、活きていれば全体に黄色味を帯びているに対し、シラウオはシラウオ科で、背びれと尾びれの間に脂びれがあり頭が尖っているので、名前は似ていますが、見ればすぐにわかります。

シロウオのおすすめの食べ方
シロウオは踊り食いが非常に有名ですが、稀に顎口虫が寄生していることがありますので、正直お勧め出来ません。万が一に備え、生食する場合は-20℃以下で24時間以上冷凍することをお勧めします。
実際には加熱した方が旨味が強くなりますので、天ぷら、唐揚げ、お吸い物、卵とじなどがお勧めですが、すぐに火が通ってしまうので、加熱し過ぎないように注意して下さい。

ヒラスズキ
ヒラスズキはその名の通りスズキの仲間で、スズキより体高があることが名前の由来です。ただし、スズキが夏が旬と言われているのに対し、ヒラスズキは産卵前の晩秋から冬が最も美味しいとされています。また、スズキのように内湾や汽水域を好まず、外洋に面した荒磯にぶつかる波によって起こるサラシの中に潜んでいます。このため水揚げは本当に少なく、味も良いことから、高級魚として扱われることが多いため、スーパーなどに並ぶことはないと言っても良いでしょう。
産地としては、紀伊、高知県、長崎県などがあげられますが、産地でもお目にかかる機会は非常に少ないです。

ヒラスズキのおすすめの食べ方
ヒラスズキは上品な旨みと甘みがあることと、その値段から非常に丁寧に扱われることが多いため、お刺身や洗いなど、シンプルに生で食べるのが最も美味しいと言われています。
また、加熱しても硬くなりにくく、適度に脂が噛んでいますので、和洋中問わず、どのような料理にも合わせることが出来ます。

クロダイ
クロダイは釣りの対象としては非常に人気が高いお魚で、ほぼ全国で1年中そこそこ水揚げがあります。マダイなど比べても安価なので、沢山流通していそうですが、スーパー、業務筋ともにあまり見かける機会がないお魚です。これは、何でも食べる悪食が災いして食用としない地域があったり、特に夏場は河川などの汽水域で生活することが多いため、身が柔らかく、臭みがあることなどが敬遠される理由のようです。春先から初夏は産卵期で浅瀬に寄ってくるため、釣りの対象魚として評価は高いですが、逆に身質は最も悪い時期とされています。食べるのであれば、水揚げが少ないながらも、生活水域や植生が変わる秋から冬が最も良いとされています。
クロダイも大きさで名前が変わり、主なところでは、幼魚をチンチン、中型をカイズ、大型をクロダイと呼びますが、他のお魚と同様に明確な基準はありません。また、関西のチヌのように、大きさによって名前が変わらない地域もありますので、出世魚としての認識はほとんどありません。
また、このお魚は雄性先熟型で、1~3歳頃までは全て精巣が発達したオスで、4~5歳になると多くは卵巣が発達しメスとなります。しかし、一部は性転換せずオスのまま成長することもあります。
産地としては突出したところはありませんが、瀬戸内海などの内湾に比較的多く見られ、広島県では放流事業も行われており、プライドフィッシュにもなっています。
最近はその数が増え、海苔、牡蠣、アサリなどを食い荒らすことによる漁業被害も出ていますので、積極的な消費を図りたいものです。

クロダイのおすすめの食べ方
鮮度が良いものが手に入れば、お刺身も良いでしょう。おろしてみて皮下に脂があれば焼霜造りなどにすると美味しく頂くことが出来ますが、獲れた場所によっては臭うこともありますので、可能であれば、購入する際にどこで獲れたかを確認すると良いでしょう。多少臭いがある場合は、日本酒などで軽く洗い、カルパッチョやマリネのように薬味とドレッシングを使えば、ある程度はカバー出来ます。
冬場には脂がのると言ってもかなり控えめですので、焼物にする場合は、ムニエルやソテーなどのように油分を加えた方が良いでしょう。
煮付けにする場合は、少し濃いめの甘辛い味付けが良いでしょう。

ヘダイ
クロダイに似ていますが、全体的に白っぽい色をしていますので、シロチヌとかギンダイとか呼ぶところもあります。旬の時期のヘダイはマダイと比べても遜色なく非常に美味しいのですが、まとまった水揚げがあまりないため、ほとんどが産地で消費され、消費地に出回ることはまずありません。知名度が低いため、もっぱら安価で流通しています。
水産統計もないので、はっきりしたことは言えませんが、主に西日本での水揚げが確認されます。
ヘダイの産卵期は晩春から初夏なので、晩秋から春先のものが最も良いとされています。

ヘダイのおすすめの食べ方
風味はマダイに似ていますので、マダイと同じ料理は全て可能です。
特に旬のものは脂ののりが非常に良いので、お刺身はもちろん、焼物や煮付けなどにしても美味しく頂くことが出来ます。

マダイ
日本ではめでたい縁起の良い魚として古くから祝い事には欠かせない存在で、鯛と言えば普通マダイを指します。また、マダイの験担ぎで、色や恰好が似ているだけで〇〇鯛と呼ばれるあやかり鯛は200種以上おり、中には無理矢理すぎるものもいますが、それだけ昔から人気の高いお魚であったことが伺えます。
マダイの寿命は20~40年と比較的長く、大きいものだと100cm、10kg超えるものもいます。
水揚げはほぼ1年中あることに加え、流通の80%以上を養殖が占めているため、毎日スーパーや料理屋で見ることが出来るため、今では旬を感じにくいお魚のひとつになっています。産卵期は海域によって多少ずれますが2~6月頃で、この時期は浅瀬に集まるため、釣りの対象としても人気が高くなります。美味しい旬は産卵期直前の桜が咲く時と言われており、この頃のものは桜鯛と呼ばれ珍重されています。夏には産卵を終えて痩せてしまうため、敬遠されることもあり、代わりにこの時に旬を迎えるチダイを使うこともあります。ただし、秋になるとまた栄養を蓄えて、冬頃には身がかなり充実し、再び旬を迎えます。
産地としては、天然物は長崎県や福岡県や多いものの、いずれも全体の10%強と突出し他産地はなく、全国で平均的な水揚げが確認出来ます。このため、各地でプライドフィッシュとしての登録が見られますが、中でも有名なのは玄界灘と明石海峡で、ここは特に身質が良いとされています。養殖は西日本に集中しており、特に愛媛県が全体の半分強と突出しています。養殖物の品質は年々向上して、へたな天然物より美味しいものも増えており、各地でブランド化が進められています。

マダイのおすすめの食べ方
お刺身の場合、締めて間もないものはコリコリした食感を楽しむ分には良いでしょうが、旨みを引き出すためには、一晩くらい寝かせたほうが良いと言われています。
上品で旨味の強い白身のお魚ですので、お刺身に限らず、椀だね、煮物、焼物、蒸物、鍋物、酢の物など和洋中問わず、多彩な料理に向くのもマダイの人気が高い理由のひとつです。また、各地で郷土食としても根付いています。

コマイ
コマイはタラの仲間ですが、大きくても40cm程度と他のタラと比べると小型です。主な産地は北海道で、本州ではほとんど見られないため、北海道以外ではほとんど知られていません。このことから、北海道での呼び名がそのまま標準和名となっています。また、漢字で「氷下魚」と書くように、寒冷な水域を特に好むため、北海道であっても南部ではあまり水揚げがありません。
タラの仲間は総じて冬に水揚げが増えるのですが、コマイに限っては5~8月にもまとまった水揚げが見られます。ただし、美味しいとされる時期は、やはり産卵前の冬です。また、他のタラと同様に、真子や白子も食用とするため、産卵期のものも需要が高くなります。
干物も盛んに作られており、こちらは全国に流通しています。

コマイのおすすめの食べ方
北海道ではお刺身を食べることもあるそうですが、タラの仲間は総じて鮮度劣化が早いので、鮮度が良いことはもちろんです。またアニサキスが寄生していることもありますので、必ずー20℃以下で24時間以上凍結したものを使いましょう。
1~3月は卵や白子を味わえる時期ですので、味噌汁、煮物、鍋物などがお勧めです。
小振りなものは、頭と内臓を取って唐揚げにすると良いでしょう。

スケトウダラ
スーパーなどに並んでいるものはマダラが圧倒的に多く、スケトウダラが切身などで出回ることはほとんどありません。理由としては、クセのない白身であるためすり身需要が高いこと、干物需要も高いこと、真子はたらこや明太子の原料として需要が高いことなどが考えられます。いずれも人気商品なので、わざわざ生鮮で出荷する必要もないのでしょう。加えて、すり身や真子は国内だけで需要を賄うことが出来ないため、輸入がメインになっています。
スケトウダラは11~4月に産卵期を迎えるため、1~2月が最盛期となります。
日本海側では山口県以北、太平洋側では銚子以北で水揚げが確認出来ますが、多いのは北海道や青森県です。

スケトウダラのおすすめの食べ方
非常にたんぱくでクセのないお魚ですので、どのような料理にも合いますが、すり身に向くだけあって、旨味に欠けるのも事実です。
このため、揚物、ムニエル、ソテーなど油を加える料理の方が無難とも言えます。
タラの仲間は総じて鮮度劣化が早いので、保存する場合は冷蔵ではなく、冷凍した方が良いです。また、アニサキスが寄生していることが多く、旨味も少ないので、鮮度が良くてもお刺身はあまりお勧めできません。どうしても食べたい場合は、ー20℃以下で24時間冷凍したものを使用し、旨味を補うために昆布締めなどにすると良いでしょう。

マダラ
マダラは切身でスーパーに1年中並んでいるため、季節を感じにくいお魚のひとつになっていますが、それだけ需要が定着したとも言えます。
元々は冬のお魚の代名詞のひとつで、産卵期前後の12~2月が水揚げがピークです。冬が旬と言うこともありますが、クセのない白身で大衆的な価格であることから、特に鍋食材として人気が高いお魚です。また、白子は「タチ」などとも呼ばれ、人気が高く、鍋はもちろん、ポン酢和え、焼物、天ぷらなどでも食べられています。ただし、真子の方は産地ではそれなりに需要があるものの、見た目が真っ黒なこともあるのか、全国的な需要はありません。
産地としては北海道が全体の4割程度を占めており、これに青森県、岩手県、宮城県を加えると全体の9割を締めます。以前は国内で大量に水揚げがありましたが、年々減少していることもあり、アメリカやロシアからの輸入がかなり増えています。

マダラのおすすめの食べ方
スーパーに並んでいるものはほぼ解凍物、産地から送られてくるものも生鮮は少なく、塩蔵や解凍物が多いため、あまり美味しいものではないと言うイメージが強いかも知れません。ただし、良いものが手に入れば、どのような料理にも合わせることが出来る万能選手です。もちろん真子や白子も同様です。
タラの仲間は総じて鮮度劣化が早いので、保存する場合は冷蔵ではなく、冷凍した方が良いです。また、アニサキスが寄生していることが多いため、鮮度が良くてもお刺身はあまりお勧めできません。どうしても食べたい場合は、ー20℃以下で24時間冷凍したものを使用し、旨味を補うために昆布締めなどにすると良いでしょう。

トクビレ
トクビレは特にオスの容姿に顕著な特徴があり、背ビレと臀ビレが体に対して非常に大きく、これが特鰭(とくびれ)と名前の由来になっています。市場や料理屋では八角(はっかく)と呼ぶことが多いのですが、これはオスの身体が角ばっており、八角形に見えるところから来ています。
主な産地は北海道ですが、ホッケなどを獲る時に混獲される程度で、水揚げは決して多くありません。加えて、味がとても良いことが全国的に知られたため高値で取引されることが多くなり、関東や関西の市場に出荷されることが増えています。このため、産地である北海道では食べる機会がかなり減ったと言われています。
トクビレの美味しい時期は、産卵期明けで栄養を蓄える12~2月頃とされており、この時期のものは特に高値で取引されているようです。

トクビレのおすすめの食べ方
トクビレは全身に鋭い棘がありますので、調理する際には注意が必要でし、捌き方も特殊になります。
鮮度の良いものは綺麗な白身で、脂をたっぷり含んでいるので、お刺身にしたくなるかも知れませんが、アニサキスが寄生していることが多いので、お勧めは出来ません。どうしても食べたい場合は、-20℃以下で、24時間以上冷凍したものを使って下さい。
ただし、身からとても良い出汁が取れるため、生食より加熱調理の方が調理法としては評価が高いお魚で、一般には汁物や鍋物です。焼物にする場合は、干物に加工するとさらに旨味が増すと言われています。

ハマトビウオ
トビウオは細かく分けると数十種類もおり、その特徴は様々ですが、一見して区別することは難しいため、全てまとめてトビウオとして流通することが多いです。その中でも市場に出回り、比較的区別されているものには、トビウオ(ホントビウオ)、カクトビ(ハマトビウオ、ツクシトビウオ)、マルトビ(ホソトビウオ)などがいますが、中で最も評価が高いのがハマトビウオで、大きなものでは50cmくらいになります。
主な産地は鹿児島県の屋久島周辺から宮崎県にかけてと東京都の八丈島周辺です。ハマトビウオも回遊魚で、屋久島辺りでは11月頃から獲れ始めます。伊豆諸島では3月頃から獲れ始めて、4月が最盛期になります。トビウオと言うと夏のイメージが強いのですが、ハマトビウオは産卵期の冬から春に接岸してくるため「春トビ」とも呼ばれています。

ハマトビウオのおすすめの食べ方
新鮮なものはお刺身にすると、とても美味しいとされています。暖海性のお魚ですので、脂は少ないのですが、旨味が強く、青魚独特の生臭さも少ないのが特徴です。
加熱調理する場合は、ソテーや揚物などのように、油を加える料理が良いとされています。

マハゼ
ハゼ科のお魚は世界中で2000種を超えるとも言われており、実に多種多様な種族です。その中でも「真」が付くマハゼは代表的なお魚です。
昔は日本全国に普通に見られ、ら食用魚として親しまれてきました。江戸前の天ぷら種には欠かせないものともされていますが、今では獲れるところも数も減り、なかなかお目にかかれなくなっています。また、環境の影響を受けやすいお魚であるため、獲れる場所によっては食用に適さないことすらあります。
現在の主な産地は、松島湾、東京湾、浜名湖、伊勢湾などです。
1年中水揚げがありますが、春から初夏にかけては産卵期で身が薄くなるため、秋から冬が最も美味しいとされています。

マハゼのおすすめの食べ方
鮮度が良いものであれば、もちろんお刺身にも出来ますが、このお魚はなんと言ってもまずは天ぷらです。クセのない上品な白身で、揚げたてはホクホクした食感が楽しめます。
また、小さなものは、古くから佃煮や甘露煮にして楽しまれています。

アラ
アラはハタ科の中で1属1種で、大きくなると1mを超えることもあります。味の評価はとても高く、大きなものは超高値で取引されることもある高級魚です。
九州ではアラと言うとクエを主に指し、加えて九州の一部地域ではアラのことをタラと呼んだりするため、九州では名前だけでなく、実物を見て確認しないとややこしいことになりそうです。
アラの成魚は長崎県や鹿児島県に比較的多く見られ、小さなものは山口県や福井県など日本海側で見られます。小さなものは時にまとまって水揚げされることもあり、その場合は比較的安価で流通することもあります。ただし、いずれの場合も産地でほとんど消費されてしまうため、消費地でお目にかかる機会はほとんどなさそうです。
美味しい旬の時期は脂がのる秋から冬にかけてです。

アラのおすすめの食べ方
大きなものは高値で取引されることが前提ですので、活物か活〆の流通が基本です。このため、すぐに調理すると鮮度が良すぎて身が反り返ったりしますので、どのような料理をするにしても、少なくとも1~2日寝かせた方が良いでしょう。
旨味がとても強いお魚ですので、大きなものはまずはお刺身がお勧めです。加熱調理する際は、味付けは控えめにするくらいで十分です。
小さなものであっても、鮮度が良ければ大きなものと同様の調理で良いでしょう。

キジハタ
キジハタは、非常に味がよく、水揚げも少ないため、特に活物など鮮度の良いものは高級魚として流通することが多く、産地でもなければ一般の食卓に並ぶことはまずありません。
主に福井県あたりから九州にかけての日本海沿岸や瀬戸内海で水揚げが見られますが、前述した通り、その量はわずかです。
美味しい時期は秋から冬の寒い時期とされていますが、少ないながらも1年中水揚げがあり、また身質が大きく変化することもありません。しかし、夏の産卵期だけしてどうしても身が痩せてしまうため、この時期のものと、産卵明け早々のものは避けた方が無難かも知れません。ただし、産卵明けは食性が戻るため、水揚げが増える傾向にあるため、少ないながらも見かける機会が増えます。

キジハタのおすすめの食べ方
キジハタは、クセや臭みがなく、引き締まった肉質が特徴です。活物は身が反り返ることもあるので、1~2日寝かせてから調理した方が良いでしょう。また、小さな鱗がビッシリと付いており、取り除き損ねると食味が悪くなりますので、丁寧に取り除くことが必要です。
旨味が強いお魚ですので、どのような料理にも合わせることが出来ます。また、皮下の脂やアラからも良い出汁が出ますので、骨と内臓以外は余すことなく食べることが出来ます。

クエ
クエはハタの仲間の大型魚で、1mを優に超えるものもいます。九州ではアラとも呼ばれ、主に冬場の鍋料理ではとても人気が高く、特に大きなものはかなりの高値で取引されています。
和歌山県や五島列島などでは養殖もされていますが、その量もわずかで、養殖物であって高価です。
主な産地は、鹿児島県、長崎県、高知県など主に西日本です。水揚げはがほとんどなきに等しい状態で、あったとしてもほとんどが高級料亭直行のため、なかなか口にすることは出来ません。
クエは鍋料理で知られていることから、冬に美味しい魚というイメージが強いのですが、身質は1年を通して大きく変わることはありません。ただし、数が少ないこともあるため、資源保護の観点で春から夏の産卵期は避けた方が良いでしょう。

クエのおすすめの食べ方
クエは活物か活〆の流通が基本のお魚です。このため、すぐに調理すると鮮度が良すぎて身が反り返ったりしますので、どのような料理をするにしても、少なくとも1~2日寝かせた方が良いでしょう。また、1尾丸ごと購入するのは無理な話なので、購入される場合は専門店で柵にしたものを分けてもらうと良いでしょう。
鍋料理はもちろんのこと、お刺身や煮物、焼物、揚物など、どのような料理にも合わせることが出来る万能魚です。
また、は捨てるところが無いお魚と言われており、アラはもちろん、調理法によっては鱗、胃袋、肝も美味しく食べられます。
鱗はサクサクになるまで揚げると、香ばしくなり、美味しく頂くことが出来ます。

スジアラ
沖縄県ではアカジンミーバイと呼ばれ、ハマダイ(アカマチ)やシロクラベラ(マクブー)とともに沖縄三大高級魚として知られています。本州では水揚げがほとんどないため、馴染みはありませんが、入荷した時には、沖縄県同様に高値で取引されているようです。
主な産地は沖縄県、鹿児島県の島しょ部です。沖縄県では養殖も始まっており、2016年には完全養殖にも成功していますが、まだその量はわずかです。
スジアラは暖海系のお魚のため、ほぼ1年中水揚げがあり、身質の変化もそうありませんが、夏から秋にかけては産卵期に当たるため、身が痩せていることが多いらしいです。決して安くないお魚ですので、この時期だけは避けておいた方が無難でしょう。

スジアラのおすすめの食べ方
鮮度が良過ぎると、身が反り返ったり、加熱した際の身離れが悪かったりしますので、サイズにもよりますが、どのような調理をするにしても少なくとも2~3日は寝かせた方が良いでしょう。
非常に上品な白身ですので、お刺身にした場合には、少し物足りなさを感じる可能性もあります。その時は、カルパッチョやマリネなどのように少し味を加えた方が良いでしょう。
加熱調理も同様で、油を加えたり、少し濃い目の味付けをした方が美味しく感じられることもあります。

ハタハタ
ハタハタは、秋田の伝統調味料である塩汁(しょっつる)の原料としても有名です。漢字では「鰰」と書きますが、これは雷やいかずちを意味する霹靂神(はたたがみ)に由来しているとされています。漁期であり、産卵期である11~12月は雪の前に雷が鳴ることが多く、その時期に沿岸に押し寄せてきたものを獲ることから、名付けられたと言われています。
ハタハタと言う呼び名は、主に秋田県など北日本の呼び方で、兵庫県から島根県など山陰地方ではシロハタとかシラハタと呼ぶこともあります。
美味しいとされる旬の時期は産地で異なり、秋田県周辺は11〜1月、山陰地方は3〜5月となります。秋田県のハタハタは産卵のためメスは抱卵しており、卵をブリコと呼び珍重します。山陰地方のものは産卵期とは逆になるため身が充実しています。このため、卵を楽しむの冬の秋田県周辺のもの、身を楽しむのであれば春から初夏の山陰のものを選ぶと良いでしょう。

ハタハタのおすすめの食べ方
冬場はブリコが楽しめる季節ですので、秋田県や北海道のもので、腹が大きく膨らんでいるものを選びましょう。
淡白でよく締まった身は鱗が無いので、ヌメリを洗い落としたらそのまますぐに調理出来ます。しょっつる鍋や味噌煮などの郷土料理として親しまれている他、熟れ寿司などにも調理されます。
1-1-scaled.jpg)
ヒメジ
ヒメジは赤い体色とアゴのひげが特徴の見た目がとても艶やかお魚で、北海道から九州までの沿岸に広く分布しており、投げ釣りなどでもよく見かけるお魚です。しかし、小さい上に、まとまったて水揚げされるところも少ないことなどから、雑魚扱いされ廃棄されてしまうこともあります。特定地域を除けばスーパーなどに並ぶことはまずないので、国内ではマイナーなお魚ですが、ヨーロッパでは人気が高く、ムニエルや揚物などで良く食べられています。
水揚げ統計はとられていないため、産地もはっきりはしていませんが、冬場の底曳網漁で混獲されることが多く、この漁が盛んな日本海側では比較的目にする機会が多いです。
また、ヒメジは夏から秋が産卵期のため、晩冬から初夏頃が最も身質が良いとされていおり、特に冬は底曳網の漁期とも重なります。

ヒメジのおすすめの食べ方
お魚自体はクセのない白身ですので、どのような料理にも合わせることは出来ます。
少し小さいお魚なので、面倒ですが、鮮度が良いものが手に入ればお刺身がお勧めです。皮は少し硬いので、付けたままにするのであれば湯引きではなく、焼霜造りが良いでしょう
揚物にする場合は、二度揚げすると、頭も骨も美味しく頂くことが出来ます。
山口県では金太郎と呼ばれ、干物に加工され、良く食べられているようです。

ヒラメ
ヒラメはお魚の中でも高級な部類として知られていますが、それは冬に限った話です。春から初夏の産卵期と産卵明けの夏は身が痩せているため、猫マタギとまで言われ敬遠される傾向にあります。ただし、これは天然物に限った話で、養殖物で季節を気にする必要はほとんどありません。
天然物の産地は、北海道、青森県、宮城県など北日本が多く、各産地ではブランド化も進められています。また、輸入も多く、韓国からは活で、アメリカ、中国からは鮮魚としても入荷しています。
養殖はヒラメ全体の流通量の20%程度で、主な産地は大分県、鹿児島県、愛媛県などです。平成26年前頃にクアド(粘液胞子虫)による食中毒被害が急増し、販売を控えるところが増えたため、養殖はピーク時の7割ほどまで減少しています。ただし、クアドにより食中毒被害は、令和3年以降ほとんど確認されておらず、心配する必要はあまりなさそうです。
※クドアが寄生したヒラメを非加熱、または加熱不十分の状態で食べると、数時間程で一過性の下痢や嘔吐を引き起こしますが、症状は軽度で、多くの場合、発症後24時間以内に回復し、後遺症もないとの事例が報告されています。なお、養殖ヒラメの場合は筋肉1グラムあたりのクドアの胞子数を1.0×10の6乗個以下とすることが定められています。

ヒラメのおすすめの食べ方
寒い時期のヒラメは脂ののりも良く、身も肥えているので、大きくて鮮度が良いものであれば、まずはお刺身がお勧めです。もちろん、ヒラメと言えば縁側のお刺身も外せません。ただ、どうしてもクアドが心配だと言う場合には、ー20℃以下で4時間以上冷凍するか、しっかりと加熱調理ことをお勧めします。
お刺身には難しい小さなものでも、旨味がしっかりある時期ですので、焼物、煮物、揚物など何でも楽しむことが出来ます。

ハマダイ
沖縄県ではアカマチと呼ばれ、スジアラ(アカジンミーバイ)やシロクラベラ(マクブー)とともに沖縄三大高級魚として知られています。水揚げが少ないため知名度はかなり低いのですが、その上品な白身は評価が高く、沖縄県以外でも、ほとんどがすし店など高級料理店向けとなり、スーパーなどに並ぶことはまずありません。
主な産地は、伊豆諸島、小笠原諸島、鹿児島県、沖縄県などです。
暖海系のお魚ですので、1年を通して身質に大きな違いはないとされていますが、産卵期が5~8月頃であることを考えると、身が充実して美味しい時期は産卵前の冬から春にかけてと思われます。

ハマダイのおすすめの食べ方
旨みが強く、血合いも少ない白身ですので、まずはお刺身がお勧めです。皮は赤く綺麗で、柔らかい上に、皮と身の間に旨味が多いので、湯霜造りにすると良いでしょう。
加熱しても硬くなりにくい身質ですので、煮物、焼物、揚物などどのような料理にも合わせることが出来ます。また、アラからはとても良い出汁が取れますので、スープなどで堪能して下さい。

シロサバフグ
フグと言うと高級魚のイメージがありますが、シロサバフグはとても安価で、スーパーなどにもよく並びます。昔は毒のないフグとして流通しており、肝も食べられていたと言われていますが、毒を持つ近縁種の存在や、海域によっては毒を持つことなどが確認されたため、現在では法律によって無毒な筋肉と皮、精巣のみが食用として認められています。
シロサバフグは、フグの中では最も多く流通していると言っても良いくらいで、ほぼ1年中水揚げがあります。産卵期は初夏ですので、身が充実するのは秋から春先までとなりますが、産卵期であっても多少身が痩せるくらいで身質に大きな変化はなさそうです。
統計資料がないので、はっきりしたことはわかりませんが、福岡県、長崎県など東シナ海で比較的水揚げがあるようです。ただし、加工品として流通しているものの多くは中国や台湾で水揚げされたものです。

シロサバフグのおすすめの食べ方
食用のフグの中では小型で、身に水分が多いため、いくら鮮度が良くても、そのままではお刺身には不向きです。お刺身にする場合は、塩や昆布などで水分を抜く下処理が必要です。また、フグ全般に言えることですが、数日寝かせた方が旨味が増すとされています。
逆に水分が多いための利点もあります。加熱しても身が硬くなりにくいため、鍋、揚物などには適しています。ただし、焼物にする場合は、水分を幾らか抜いた方が身離れも良くなり、旨味も増すようです。
※フグは猛毒のテトロドトキシンを持っているため、調理は必ず免許を持っているプロにお願いしましょう。

トラフグ
フグの中で最も高級で「ふぐの王様」と称されるのがトラフグです。
トラフグと言うと山口県の下関市が有名ですが、決して水揚げが多いわけではなく、あくまで流通拠点として取り扱いが多いだけです。昔からフグには毒があることが知られており、安土桃山時代には食用禁止令が出ていたとも言われています。しかし、下関市ではひっそりと食べ続けられていたらしく、明治時代になって、初代内閣総理大臣の伊藤博文が山口県を訪問した際に内緒で出されたふぐ料理の美味しさに驚き、山口県知事に働きかけて明治21年(1888年)に山口県だけ解禁になったとされています。そレが元で下関に集まるようになったとされています。
トラフグだけの統計資料がないため、産地ははっきりはしませんが、以前は西日本に集中していましたが、近年では東北などでも見られるようになっており、これに伴い東日本での需要も高まっているようです。
現在は養殖も盛んに行われているため、1年中流通していますが、美味しい旬は、秋の彼岸から春の彼岸までと言われています。また、産卵前の1~2月であれば白子を楽しむことも出来ます。ちなみに養殖が最も盛んに行われているのは長崎県です。

トラフグのおすすめの食べ方
淡白な身質ですが、しっかりとした旨みと甘味を兼ね備えております。ただし、鮮度が良いと旨味を感じにくいことから、下処理後に数日寝かせると良いとされています。
寒いこの時期のお勧めは何と言ってもふぐちりです。フグと言うと料理屋で食べるイメージが強いかも知れませんが、鍋であればご家庭で楽しむことも出来ます。
※フグは猛毒のテトロドトキシンを持っているため、調理は必ず免許を持っているプロにお願いしましょう。

マフグ
マフグは「ふぐの女王」と称されており、最高級のトラフグよりも強い甘みを持っているとも言われています。養殖はされていませんが、トラフグと比べて水揚げ量も多いため、比較的安価で流通しており、特に産地ではシーズンになるとスーパーなどにもよく並ぶようです。
産地として有名なのは山口県で、中でも萩市が突出して多く、プライドフィッシュにもなっています。
水揚げが増えるのはやはり需要期である冬場ですが、山口県での最盛期は2~4月です。

マフグのおすすめの食べ方
トラフグと比べると身が柔らかいのが難点と言えば難点ですが、水分を軽く抜く処理をすれば十分にカバー出来ます。また、そこまでせずとも、実が柔らかいことを逆手に取れば、無理に薄造りにせず、普通のお刺身でも楽しむことも出来ます。
皮やヒレは有毒のため食用にはなりませんが、それ以外の一般的なフグ料理は楽しむことが出来ます。
※フグは猛毒のテトロドトキシンを持っているため、調理は必ず免許を持っているプロにお願いしましょう。

ニゴロブナ
ニゴロブナは琵琶湖の固有種で、特に鮒寿司の原料として古くから親しまれています。鮒寿司にはゲンゴロウブナが使われることもありますが、ニゴロブナの方が骨が軟らかく味が良いとされています。滋賀県ではプライドフィッシュになっており、県内ではとても重要な食用魚です。
琵琶湖での水揚げ量は、昭和40年ごろには500トン程度ありましたが、平成元年には178トン、平成9年には18トンにまで激減しており、今では高値で取引されるようになっています。激減した原因としては、外来魚の影響や、瀬田川洗堰の操作により、産卵期に琵琶湖水位が急激に低下し、稚魚の棲むヨシ帯が干上がってしまうことなどが指摘されています。
身だけを考えるとコイなどと同様に晩秋から冬が旬となりますが、鮒寿司には子持ちのものが重宝されるため、産卵期の4~7月に水揚げが集中しています。

ニゴロブナのおすすめの食べ方
他のフナと同じように料理されるはずなのですが、ニゴロブナは鮒寿司しか紹介されていません。鮒寿司は保存食ですので、いつが美味しいと言うことはありません。

ブリ
天然のブリは春から初夏に産卵期を迎えますので、その前の冬に沢山餌を食べて、身も太り、脂がのります。しかし産卵を迎えると栄養のほとんどを真子や白子へ持っていかれるため、同じお魚とは思えないいくらい脂が落ちてしまいまので、寒ブリとして美味しく味わうことが出来るのは2月一杯くらいまでです。4~5月に抱卵した大きなものが沢山獲れて、価格も安くなりますが、冬のブリを味わった後だけに余計違いを感じてしまいます。
この時期は南下に伴い、北陸から山陰沖で水揚げが増えます。太平洋側でも取れないことはありませんが、その数はわずかです。
養殖物は生産技術の向上により1年中美味しく頂くことが出来ますので、季節はほとんど関係ありません。今ではほぼ周年スーパーに並んでいますので、季節によっては養殖物の方が美味しく感じらる場合もあります。

ブリのおすすめの食べ方
ブリは特に西日本のお正月には欠かせない食材です。お刺身、照焼き、ブリ大根などはもちろんですが、地域によってはお雑煮などに入れるところもあります。
脂ののりが最も良くなる時期ですので、少ししつこいと感じられる方には、しゃぶしゃぶがお勧めです。
※寒い時期の天然ブリにはアキサキスが寄生していることもありますので、お刺身にする場合は必ずチェックして下さい。心配な場合は必ず加熱調理して下さい。

カナガシラ
カナガシラはホウボウの仲間で、外見だけでなく、身質もホウボウと良く似ています。ただし、ホウボウと比べて一回り小さいことや、水揚げもそう多くないため、出回りはほとんどなく、産地で消費されるに留まっています。頭部の骨はかなり硬く、名前であるカナガシラ(金頭)の由来になっています。
海底に生息しているため、冬に底曳網漁が盛んになる日本海側で見かけることが出来ます。漁期が春の産卵期の丁度前ですので、身質が良い時期と重なります。

カナガシラのおすすめの食べ方
上品な白身で、甘みが強いので、鮮度が良いものが手に入れば、まずはお刺身がお勧めです、ただし、頭が大きくほっそりした体形で、大きくても30cm程度ですので、歩留まりは決して良くありません。
ただし、アラからはとても良い出汁が出ますので、小さなものであれば、丸ごと煮物にすることで、余す事無く食べることが出来ます。

ホウボウ
ホウボウは、胸びれに3本の脚のような柔らかい軟条が発達しており、これを使って海底を歩くように砂の中の獲物を方々に探し回るそうで、これが名前の由来とも言われています。また、胸ビレは非常に艶やかで、非常に大きなことも特徴のひとつで、海底で泳ぐ様は蝶々の様にも見えます。
産卵期は地域によりずれがありますが、おおむね4~6月にかけてのようですので、身が最も充実するのは冬とされており、日本海側で底曳網漁のシーズンと重なります。
水揚げ自体は1年中ありますが、頭が大きくスマートで、只でさえ歩留まりが悪いお魚ですので、産卵期及び産卵明けの身が痩せたものは避けた方が無難でしょう。

ホウボウのおすすめの食べ方
甘味が強い上に上品な白身が特徴ですので、大きくて、鮮度が良いものが手に入ればまずはお刺身がお勧めです。
また、アラなどからはとても良い出汁が出ますので、丸ごと煮付けにしても良いですし、他の旬の食材とともにアクアパッツアやブイヤベースにすると一層旨味が増します。

クロマグロ
クロマグロは、厳密にはタイヘイヨウクロマグロとタイセイヨウクロマグロの2種が存在しますが、ここではタイヘイヨウクロマグロを紹介します。
豊洲の初競りで話題になるマグロですので、ご存じの方も多いと思いますが、大きなものでは体長3m、体重400kgを超える、マグロの中では最も大きなものです。普通はホンマグロと呼ばれますが、地方によってはシビとかハツとか呼ばれることもあります。また小さなものはヨコワ(近畿から四国地方)やメジ、メジマグロ(中部から関東地方)とも呼ばれます。
天然のクロマグロは乱獲などにより水揚げは激減していますが、良いものは高級寿司店などの引き合いが非常に強く、黒いダイヤとも呼ばれ、かなりの高値でで取引されています。現在は、資源保護の観点から厳しい漁獲制限が進めらていますが、残念ながら、今のところ目に見える回復には至っていません。こういうこともあり、今では国内外問わず盛んに養殖行われるようになりました。
天然物の水揚げが多いのは、長崎県、青森県、宮城県など、青森県大間のものはブランド化され、大間マグロとして流通しており、とても有名です。
養殖の産地は長崎県、鹿児島県、高知県で、3県あわせて国内生産量の半分以上を占めています。養殖もブランド化が進められており、その中でも近大マグロが有名です。
クロマグロは夏の産卵期は身質が落ちるため、キハダとは異なり敬遠されることが多く、真冬の脂ののった時期のものの評価が非常に高くなります。

クロマグロのおすすめの食べ方
生食を基本として流通しているお魚ですので、養殖であっても非常に高価ですが、鮮度の良すぎるものは旨味に欠ける場合がありますので、切身の形状にもよりますが、3日から10日程度寝かせた方が美味しいととされています。
まずはなんといっても、お刺身がお勧めで、大きなものであれば、単に赤身赤身、トロと言った分け方ではなく、どの部位化で異なる味わいとなります。
赤身、トロは非常に高価ですが、アラに当たる部分は比較的安価で流通していますので、焼物や煮物などで気軽に楽しむことも出来ます。

ビンナガ
長い胸ビレ大きな特徴で、上から見るとトンボが羽を広げているように見えることから、トンボマグロとも呼ばれますが、ビンチョウマグロとして流通することの方が多いようです。脂ののったものは、回転寿司などではビントロと言う名前で販売されています。
マグロの中では小型の部類で、大きくても1.5ⅿ程度にしかなりません。加えて、マグロの中では最も安価で、小さなものはキハダやカツオなどとともにツナ缶の原料になります。
日本近海でも1年中漁が行われており、冷凍流通も多いので、旬を感じにくいお魚のひとつになっていますが、日本近海で脂がのるのは真冬で、夏の産卵期には非常にあっさりした味わいになります。

ビンナガのおすすめの食べ方
とにかく身が柔らかく、身割れしやすいですので、注意して下さい。また、薄ピンク色の物より、白いものの方が脂がのっていますので、購入される際に良く確認した方が良いでしょう。小型の物や、尻尾、腹回りは硬い筋がしっかり入っているので、お刺身には向きませんので、揚物などにすると良いでしょう。
お刺身にする場合は、筋が少ない部位を選ぶのが賢明ですが、筋がある場合は角切りやタタキなどにして、筋を感じにくいようにした方が無難です。
また、旨味が足りないと感じる場合には、漬けにすると良いでしょう。

マトウダイ
マトウダイと言う名前の由来は、顔が馬の様に見えることから馬頭鯛(マトウダイ)と言う説と、体の真ん中あたりにある白く縁どられた黒い円状の斑紋が、弓を射る時の的に見えるからと言う説がありますが、いずれかははっかいりとしていません。ただ、名前の由来にもあるように、少し変わった風貌に加えて、頭がとても大きく、ぺったんこな特徴的なお魚です。
日本海側で冬に底曳網漁が始まると、出回りが若干増えますが、消費地に出回るほど大量に獲れることはなく、産地でお目にかかれる程度です。
やや暖かい海域を好むようで、主な産地は太平洋側で静岡や和歌山など、日本海側で北陸、山陰、長崎県などです。
産卵期は地域により違いがありますが2~5月頃にかけてで、寒いところほど遅くなります。産卵期に水揚げが増えるところもありますが、ただでさえ平ぺったいところに抱卵してしまうと、かなり身が痩せてしまいますので、美味しい時期は冬から初春までとなるでしょう。

マトウダイのおすすめの食べ方
身がとにかく薄く、頭が大きいお魚ですので、歩留まりが極端に悪いのが難点です。ただし、その身は透明感のある白身で、ほのかな甘味に加えて、上品でねっとりした口当たりが楽しめますので、鮮度が良くて大きなものが手に入れば、とにかくお刺身がお勧めです。
小さなものは、揚物、煮物にすると美味しく頂くことが出来ます。

マナガツオ
カツオと言う名前が付いていますが、カツオとは似ても似つかぬ容貌に加え、身質も全く異なります。江戸時代に書かれた「本朝食鑑」によれば、「カツオの鱠(なます)は世間で広く知られているが、これは鮮度のいいカツオでなければならない。京都は海から遠く、新鮮なカツオが手に入らないので、代わりの魚のカツオに学び鱠で食べている。」とされており、ここから学鰹(まながつお)と名付けたと記されています。
体は楕円形で側扁し、背ビレと臀ビレがカマのような形に大きく発達しています。また、頭部が小さく、それに準じて目や口も非常に小さくなっています。また、一見するとウロコがないように見えますが、実際には燻銀色の細かいウロコが沢山あります。ただし、非常に剥がれやすいため、特に網で獲られたものは地肌がむき出しになっていることもあります。
主な産地は東シナ海に面した九州東岸から南九州と、瀬戸内海ですが、いずれの海域も水揚げが減少しており、鮮度の良いものは高値で取引されることが非常に多くなりました。
漁期は地域により異なります。瀬戸内海では産卵のため入って来る初夏から秋までで、少ないながら水揚げは増えるものの、やや身が薄く、脂ののりもいまひとつで、あっさりした味わいになります。東シナ海は12月頃から翌春先までで、この時期は脂ののりも良く、最も身が充実した季節となります。

マナガツオのおすすめの食べ方
上述した通り、細かい鱗が残っているので、しっかりと取っておく必要があります。また、身が非常に柔らかいので、丁寧に優しく取り扱う必要があります。
みこの時期は、脂がのり、身が最も充実する時期ですので、どのような調理にしても美味しく頂く音が出来ます。アラは煮物やお吸い物にすると、良い出汁が出ますので、美味しく頂くことが出来ます。また、マナガツオの骨は非常に柔らかく、二度揚げすれば食べることが出来ますので、ヒレなども含めて唐揚げにすると良いでしょう。。

アカムツ
アカムツは、口の中を覗くと奥が真っ黒になっており、これが流通名のノドグロの由来となっています。また、名前にムツと付きますが、ムツ科のお魚ではなくホタルジャコ科のお魚です。味がとても良く、白身のトロと呼ばれるほど脂がのっていることから、もっぱら高級魚として取引されています。
アカムツは大きいものだと50cmを超えることもありますが、普通市場に出回るものは大きくても30cm前後で、20cmくらいのものが多いです。
産地は、富山県などの北陸から、島根県などの山陰地方など日本海側で多く獲れ、太平洋側ではあまり見られません。各地でブランド化も進められており、島根県の「どんちっちノドグロ」、長崎県の「紅瞳」などがあります。
また、近年はその人気の高さからか、韓国からの輸入も増えており、国産と比べると安価なことから、スーパーや回転寿司などで見かけることもあります。
美味しい旬の時期には諸説あり、晩秋から冬と言う説があるかと思えば、真逆の産卵前7~8月と言う説もあります。また、子持ちの煮付けを重宝する地域では9月頃を最良とする地域もあります。
ただし、1年中脂がのっていることは事実ですので、その時々の身質に合わせた調理をすれば、年中楽しむことが出来るのは間違いないでしょうが、ここでは春、夏、冬を旬として紹介します。

アカムツのおすすめの食べ方
冬から春は産卵期とは真逆の時期ですので、最も身質が安定しており、様々な料理を楽しむことが出来ます。
アカムツは、皮と皮下の脂に旨味が詰まっていますので、どのような料理をするにしても皮は付けておいた方が良いでしょう。

クロムツ
透明感のある白身ですが、冬のものは脂が多いため白濁することもあり、鮮度が悪いと勘違いされることもあるようです。
皮は柔らかく、皮と皮下の脂にも旨味がたっぷり詰まっていますので、どのような料理をするにしても皮は付けておいた方が良いでしょう。
身はふんわりと柔らかく、加熱しても身が硬くならず、身離れも良いので、どのような料理にも合わせることが出来ますが、クロムツの風味を楽しむためには、濃い味付けや油を加える料理は避けた方が良いかも知れません。

クロムツのおすすめの食べ方
透明感のある白身ですが、冬のものは脂が多いため白濁することもあり、鮮度が悪いと勘違いされることもあるようです。
皮は柔らかく、皮と皮下の脂にも旨味がたっぷり詰まっていますので、どのような料理をするにしても皮は付けておいた方が良いでしょう。
身はふんわりと柔らかく、加熱しても身が硬くならず、身離れも良いので、どのような料理にも合わせることが出来ますが、クロムツの風味を楽しむためには、濃い味付けや油を加える料理は避けた方が良いかも知れません。

メジナ(総称)
メジナは、関西ではグレと呼ばれ、磯釣りの対象魚としては人気がとても高く、釣人の間では味の良いお魚とされているのですが、何故か料理素材としては人気がなく、市場価格はかなり低いです。
近縁種にクロメジナとオキナメジナがいますが、市場価値が低いこともあってか、区別されずに流通していることも多いようですので、ここでは3種まとめてメジナとして紹介します。
小さなものは堤防付近でも見られますが、磯周辺が漁場となるため、漁自体が困難でまとまった水揚げがありません。これも市場価値が低い原因かも知れません。
産地と言うより、釣場として有名なので、伊豆半島、紀伊半島、山陰沿岸、九州沿岸などです。
雑食性のため、食べたものの影響が身に出やすくなります。夏は磯周りの生物を食べるためか磯臭いとされて評価が低く、冬場は海藻が主体となるため臭みがなくなると言われていますが、釣餌としてオキアミなどが多用されているため、有名な釣場のものは、磯臭いものが少なく、1年中安定しているように感じます。
美味しい時期は産卵前の冬で、最も脂がのるとされていますが、これも釣餌の影響からか、1年中脂がのっている個体も存在するようです。ただし寒い時期のもので、しっかり処理されたものは身の締りがとても良く、美味しいです。

メジナのおすすめの食べ方
自分で釣るか、知り合いにメジナ釣りが好きな人でもいない限り、高鮮度のメジナを手に入れるのは難しいですが、寒い時期のメジナは身の締りも良く、脂もしっかりのっていますので、特にお刺身と煮物は絶品です。ただ、小さなものは旨味に欠ける場合がありますので、そのような時は、マリネやカルパッチョなどにすると良いでしょう。
さらに小さなものは、唐揚げやあんかけにすると美味しく頂けますが、骨や頭はとても硬いので、あらかじめ外しておいた方が良いでしょう。

クロメバル
かつて、クロメバル、シロメバル、アカメバルの3種は同一種のメバルとされていましたが、2008年にそれぞれ別種として分類されました。3種ともに同じような体形をしていますが、名前に付いた色で見分けることが出来ます。
クロメバルは、本州、九州、四国の沿岸各地で水揚げがありますが、特に多いのは瀬戸内海沿岸です。
メバルは卵胎生のお魚で、初冬に交尾し、12~2月に稚魚を出産します。美味しい旬は交尾前の秋とされていますが、この時期は残念ながら水揚げが期待出来ません。
メバルを春告魚と呼ぶ地域もありますが、これは出産のために浅瀬に寄って来る物を指しており、美味しい時期を指しているものではありません。
秋から冬は抱卵または、稚魚を抱えているものが多いのですが、栄養を補うため食性が活発となり、それなりに身はふっくらしています。水揚げが多いことも考慮して、旬と言えるのは秋から冬ではないでしょうか?

クロメバルのおすすめの食べ方
メバル料理で外してはならないのは煮付けです。非常にオーソドックスな料理ですが、独特の旨味に加え、身離れが非常に良いため、煮付け用のお魚としては超一級品です。
鮮度が良ければお刺身もお勧めですが、大きくても20cm程度と小さいお魚で、かつ頭が大きいので可食部分が非常に少なくなるのが難点です。ただし、しっとりして甘味のある白身は、とても上品で美味しいです。
唐揚げにする場合は、カマやヒレなどにかなり鋭利な箇所がありますので、取り除いておいた方が良いでしょう。

アコウダイ
アコウダイは日本固有種で、近縁種にはオオサガ、サンコウメヌケ、バラメヌケなどがおり、良く似ていることから「メヌケ」と同じ名前で呼ばれることがあります。いずれも深海に棲息しているため、水揚げの際に水圧の影響で、目が突き出してしまう(目が抜ける)様から、そう呼ばれるようになったとされています。
以前は沢山獲れたらしく、関東では煮物用の惣菜魚として人気があったらしいのですが、資源の減少に伴い、今では滅多に見ることすらできなくなり、超高級魚となりました。
産地としては、千葉県、伊豆諸島、神奈川県、静岡県などがありますが、いずれも水揚げはほとんどありません。
産卵期と漁期はは冬から春で重なります。これは、普段1000m程度の深海に棲んでいますが、産卵期には200m程度の深さまで上がってくるため、比較的漁がしやすくなるためです。身が充実するのは夏なのでしょうが、この時期のものの入手は極めて困難です。

アコウダイのおすすめの食べ方
大きさにもよりますが、下処理をした後、2~3日ほどで寝かせたほうが良いとされています。また、皮と皮下の脂に旨味があるので、どんな料理をするにしても皮は付けたままが良いとされています。ただ、身が非常に柔らかく、身割れしやすいので、下処理時に塩などで軽く水分を抜いてあげた方が良いでしょう。
ただし、水分が多いことが幸いして、加熱しても硬くなりにくいので、煮物、焼物など、様々な料理に合わせることが出来ます。

シマゾイ
ソイの仲間はよく似ているものがおおいため、区別されずに流通することも多いのですが、シマゾイは他体の色彩が特徴的で判別しやすいため、他のソイとは区別されて流通しています。
主な産地は北海道で、ソイの中でも安い部類に入ります。この手のお魚は産地でほとんど消費されてしまうのが常なのですが。関東や関西の市場に並ぶことも多く、同様に安価で流通しています。産地から遠く離れた消費地市場で流通する場合は、広く知られているか、高級魚の場合が多いのですが、シマゾイはどちらにも当てはまりません。恐らくですが、沢山獲れて地元での消費が難しい場合に、他のソイと一緒に送り付けているのだろうと推察されます。
統計など詳しい情報はありませんが、北海道では秋から冬にまとまった水揚げがあるとされています。

シマゾイのおすすめの食べ方
お刺身にする場合は、鮮度が良いものが条件ですが、安価での流通が前提ですので、産地であってもかなり難しいでしょう。どうしてもとなると自分で釣るか、釣りが好きな人に頼むくらいしか手がないでしょう。
メバルの仲間ですので、おすすめ料理としては煮付けが鉄板です。アラからは良い出汁が出るので、味噌汁などにすると良いでしょう。小さなもの1尾丸ごと使える料理が適当ですので、唐揚げや、アクアパッツァなどが良いでしょう。

ヤナギノマイ
ヤナギノマイの名前は、海底に生えるヤギ類やウミシダ類を「柳」に見立て、その中を群栄する様子から付けられたと言われています。
主な産地は、東北から北海道ですが、鮮度落ちが早いこともあり、そこそこ水揚げがあるものの、産地での消費に留まっており、消費地に出回ることはまずありません。
ヤナギノマイも他のメバルと同じように卵胎生魚で、12月頃に交尾し、4~7月に出産します。このため、身が充実し美味しい旬の時期は冬となります。

ヤナギノマイのおすすめの食べ方
鮮度落ちが早いことなどから、お刺身にするには自分で釣るくらいしか方法がないと言われていますので、一般に流通しているものは基本的に加熱調理用となります。こういったことから、安価で流通しており、味自体は良いので、煮物、焼物、揚物など、いわゆるメバル料理であれば何でも出来ます。
ただし、上述したように産地以外での流通はほとんどないので、消費地でお目にかかることは滅多にありません。

ユメカサゴ
ユメカサゴは、目が輝く姿がまるで夢を見ているようだとされ名前が付いたと言われていますが、正直定かではありません。ただ、生きているものは確かに目がキラキラしており、特徴的であることには間違いありません。
釣物で大きなものは高値で取引されることもありますが、底曳網で獲れたものや小さなものの価格は非常に安価で、惣菜魚として人気があります。
また、口の中が黒いこともあり、茨城県や神奈川県などではノドグロと呼ばれていますので、地域によっては名前だけで判断しないよう注意が必要です。
主な産地は福岡県から長崎県にかけての日本海沿岸や福島県から茨城県にかけての太平洋沿岸、愛知県などです。
産卵期は冬なのですが、この時期に底曳網漁などで水揚げが増えるため、冬が旬とされています。

ユメカサゴのおすすめの食べ方
大きくて鮮度が良ければお刺身で食べることも出来ますが、水分が多いお魚ですので、下処理時に塩などで軽く抜いておいた方が良いでしょう。
基本的には加熱調理用のお魚で、加熱しても身が柔らかく、身離れも良いので、焼物、煮物、揚物、蒸物などに向きます。

アマエビ(総称)
ここでは国産のアマエビを紹介しますが、アマエビと言う呼び名は流通名で、標準和名はホッコクアカエビ、もしくホンホッコクアカエビです。前者はロシアから日本の日本海側で獲れます。後者は北欧や北米など北大西洋で獲れ、スーパーや回転寿司などでよく見られるのはこちらです。この2種は本当にそっくりで、ぱっと見で区別するのは難しく、産地で判断するくらいしか出来ません。
国産のアマエビはは1年中水揚げがありますので、お目にかかる機会が多そうな気はしますが、輸入品と比べてかなり高いこと、冷凍や加工品での流通がほとんどないこと、鮮度落ちが早いことなどから、産地や料理専門店でもない限りお店に並ぶことはまずありません。したがって、食べたい場合は料理専門店に問い合わせして入荷がある場合に予約するか、水揚げが多い時期に産地に行くくらいしか手がありません。
美味しい旬の時期についても悩ましいくらい複数の説があります。晩秋から冬にかけての海水温度が下がる時期が良いと言う説、北陸地方では休漁明け9月上旬から10月と言う説、北海道では水揚げピークの5月などと言う説などがありますが、いずれも明確な根拠はありません。ひとつ言えることは、抱卵しているものは間違いなく身が痩せていると言うこと、産卵後はさらに身が痩せると言うことです。ただし、卵は食べることがありますので、産卵明けの6~8月だけは避けた方が無難と言うことになりそうですので、ここでは産卵明けの夏以外を旬として紹介します。

アマエビ(総称)のおすすめの食べ方
アマエビは基本生食用ですので、鮮度が命です。鮮度が良ければ、頭を抜いたときに背ワタも一緒に獲れますし、芳醇なミソも一緒に味わうことが出来ます。抱卵したものであれば、卵のプチプチ食感も一緒に楽しむことが出来ます。ただし、適正に管理することが出来れば、1日程度置いた方が、獲れたてより甘味が増巣と言われています。
お刺身には少し厳しい場合は、殻付きのまま調理すると良いでしょう。お勧めは塩茹で、唐揚げ、炒め物、汁物などです。ただし、頭の先のトゲは口に刺さることがありますので、取り除いておいた方が良いでしょう。

トヤマエビ
トヤマエビは、一般にボタンエビとして市場に流通しています。これは、ボタンエビの水揚げが減少したため、良く似ているトヤマエビを代用品として流通させている内に、流通名として定着してしまったことによるものです。ちなみにトヤマエビの名前の由来は、富山湾で研究用として最初に採捕されたことによるもので、富山県周辺に多く生息していると言う意味ではありません。実際のところ、富山県の水揚げはわずかで、大半は北海道となっています。
産卵期は早いところで4月頃から始まりますが、期間が非常に長く、一旦抱卵すると産卵まで10ヶ月程度かかりますので、正確な旬の時期についての把握は困難です。ただし、卵も味わいのひとつですので、産卵明けで身が痩せた物を除けば、いつでも美味しい時期と言って良いでしょう。北陸などではズワイガニ漁が出来ない時期に漁をしたりするので、金沢周辺では3月下旬から夏にかけて水揚げの最盛期を迎えます。

トヤマエビのおすすめの食べ方
ボタンエビの代用品とはいえ、水揚げは決して多くなく、食味の良さから高級品として取引されていますので、料亭や寿司店以外でお目にかかることはまずありません。
鮮度の悪いものが流通することはまずありませんので、まずはお刺身がお勧めになります。
頭は加熱することでミソまで美味しく頂くことが出来ますが、ボイルすると風味が失せてしまうので、加熱する場合は、焼くか、電子レンジが良いとされています。

イセエビ
イセエビと言う名前はミナミイセエビ属の総称として使われていることが多く、標準和名のイセエビのみを指すと言うことはまずありませんが、ここでは本家本元のイセエビを紹介すます。
イセエビは、その長いヒゲと曲がった腰から老人に見立てられ、長寿にあやかると言う意味を込めて、結婚式の披露宴や正月など祝い事には欠かせない食材です。主な産地は三重県、千葉県、和歌山県、静岡県ですが、三重県、千葉県、和歌山県でほぼ全国の半分を占めています。また三重県では県の魚に指定しています。
漁期は資源保護のため、各地で産卵時期の初夏から夏の間禁漁とされており、それ以外の時期が旬となります。地域で若干異なりますが、主なところでは、三重県で10月1日から4月末日、千葉県で8月1日から5月末日、和歌山県で9月15日から4月末日、南伊豆で9月16日から4月末日、宮崎県で9月1日から4月15日、徳島県で9月16日から徳島5月14日などとなっています。
産卵期は夏なので、8~9月頃はまだ身質が改善されていない場合もあるかも知れませんので、実際の食べ頃は10月くらいから内子が入りだす3月前までではないでしょうか。

イセエビのおすすめの食べ方
イセエビは、どんな料理をするにしても、とにかく元気よく生きていることが肝心です。ただし、長い間生簀にいると身が痩せてしまいますので、獲れたてもののがベストです。死んだ者は、活〆でもない限り味わいが悪くなることが多いので、とにかく注意して下さい。いつ死んだかわからないものならば、鮮度の良いうちに冷凍したものの方が随分マシです。
イセエビと言うとまずはお刺身を思い浮かべる方も多いでしょうが、とにかく歯応えと旨味が強いので、焼物や揚物などにしても美味しく頂くことが出来ます。ただし、尻尾の可食部位はとても少ないので、頭や殻も有効利用しなければなりません。半分に割って、炉端焼き風にすれば、ミソと身を一緒に味わうことも出来ますし、ソースを塗ってテルミドールに仕上げても良いでしょう。殻や脚は殻はとても良い出汁が出ますので、汁物には最適ですし、大きなものであれば脚の身をカニのように食べることも出来ます。

クルマエビ
クルマエビの最大の特徴は頭胸甲から腹節(胴)にかけて入っている褐色の縞模様で、胴を丸めた時にこの縞模様が車輪に見えることが名前の由来となっています。また、尾の先は茶色、黄色、青と鮮やかな色合いで、それを赤い毛が美しく縁取っています。無論、見た目の美しさだけでなく、味も評価も非常に高いです。
しかし、開発などによる環境の変化から、天然物の数は大きく減っており、現在流通しているものは、80%以上が養殖です。天然物は希少性が高いこともあり、特に活物は高値で取引されます。また、養殖であっても、生産コストが高いことに加え、活物で流通させるため、物流コストも高く、いずれも高級食材として扱われています。
種苗放流を含む天然物の産地としては、愛媛県、愛知県などがあげられます。養殖は、沖縄県、鹿児島県、熊本県など温暖な地方が目立ちます。また、近縁種を含め、台湾やオーストラリアなど海外から輸入も増えており、近年では冷凍ものだけでなく、需要期には活物の空輸もあります。
美味しい旬の時期は晩秋から冬とされています。この時期のものは冬眠のために身に栄養が蓄えられており、旨味成分であるアミノ酸のグリシンの含有量が1年で最も多くなるためとされています。しかし冬眠期であるため、水揚げは少なくなりますので、養殖物がメインとなります。加えて、年末年始は最大の需要期ですので、1年で最も高くなります。逆に初夏からの産卵期は、苦みを持つアルギニンが増えて、冬の物とは大きな差が出てしまうと言われています。

クルマエビのおすすめの食べ方
クルマエビを調理する場合は、元気良く生きているものが基本となります。難しい場合は、鮮度の良いうちに冷凍したものをお勧めします。ドリップが出ていたり、黒変したものは避けましょう。また、砂地を俳諧するエビですので、調理時に背ワタはきちんと取り除いて下さい。
最初にお勧めするのはやはりお刺身です。特に活物はプリプリの食感が楽しめます。
他は、エビ料理の王道である、天ぷら、塩焼きなどもお勧めですが、お吸い物など茹でものにするとあっさりとした上品な味わいとなります。

シバエビ
シバエビは10cmくらいものの出回りが多く、大きい物でも15cmほどと小型のエビです。水揚げしてすぐのものは、透明感のある白っぽい殻に細かい黒斑点が無数に入っていますが、古くなると斑点は消えてしまいます。かつては東京湾の芝沖で沢山穫れたことから芝海老と呼ばれるようになったと言われていますが、今はほぼ見ることが出来ません。現在の主な産地は有明海と三河湾などですが、水揚げも年々減少していおり、産地であってもスーパーなどに並ぶことはあまりないようです。
産卵期は夏で、主な産地の漁期は産卵明けの10月頃から翌4月位までとなります。旬の時期は調理用途により異なるとされており、かき揚げなどに使う小さいサイズであれば冬、大きいものは春となります

シバエビのおすすめの食べ方
鮮度が良いものはお刺身に出来、上品な甘味とエビの香りが楽しめます。ただし、身に透明感はなく、くすんだグレーなので、見た目は正直良くありません。
小さなものであれば、殻が非常に柔らかいので、そのまま唐揚げ、かき揚げ、素焼きなどにするのがお勧めです。殻付きですので、風味が豊かになることに加え、サクサクとした食感を楽しめます。大きくて、殻が少し気になる場合は、他のエビ同様に殻をむいて天ぷらにすると良いでしょう。
また、身はすり身団子にしてお吸い物や揚物にしても良いです。むき身にした後の殻や頭は、素揚げにしたり、出汁用として活用することも出来ます。

ゾウリエビ
ゾウリエビは、見た目が草履(ぞうり)にそっくりなところから名付けられています。ちなみに英名もslipper lobster(スリッパー・ロブスター)とスリッパにそっくりなところから来ています。
ウチワエビと比べると、体にやや厚みがあるものの、大きさは15~20cmとほぼ同じです。ただし、殻は極めて厚く硬く、歩留まりは非常に悪いです。
また、余程ジッとしていることが多いのか、ウチワエビなどとは異なり、特に頭部周辺ににフジツボやエボシガイが付着しているものが多いです。
市場の評価は高く、産地であっても高値で取引されることが多いため、活物での流通が基本です。
産地は暖流域に集中しており、沖縄県、鹿児島県では良く見られます。ただし、本種を目的とした漁はなく、イセエビ漁の混獲ですので、沖縄県ではイセエビの解禁時期である9月から春くらいまでがゾウリエビの水揚げ時期となります。

ゾウリエビのおすすめの食べ方
死んでしまうと、臭みが出る上に、身が痩せてしまうので、とにかく生きているものが前提です。しかし、生簀で数日生かしたものは身が痩せている場合があります。
見ての通り、頭が大きく、体が小さく、殻も分厚いので、歩留まりは極めて悪いですが、まずはお刺身がお勧めです。イセエビに負けない芳醇な味わいを楽しむことが出来ます。
もちろん、塩茹で、焼物などシンプルに味わって頂いても結構ですし、変わり種では天ぷらもお勧めです。もちろん、殻からは美味しい出汁が獲れますので、汁物もお勧めです。

ガザミ
ガザミの仲間で食用として流通しているものは種類が多く、タイワンガザミ、ジャノメガザミ、イシガニ、ノコギリガザミなど多種多様です。また、本種は標準和名のガザミではなく、もっぱらワタリガニで流通しています。
ガザミ類は北海道南部以南の全国に分布していますが、主な産地は内湾で、三河湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内海、有明海などで多く見られます。県別では、愛知県、福岡県、愛媛県などです。
ガザミの産卵期は初夏から秋にかけてで、この頃は外子を抱えたメスが多くなります。夏には脱皮をするものが多いこともあり、身入りが良くて美味しいの時期は、秋に深場に戻る頃から内子が充実する冬です。しかし、冬になると深いところに潜ってしまうため、水揚げはとても少なくなります。
水揚げだけだと、浅場に移動してくる初夏から夏です。このように、旬については一概には言えませんが、身を楽しむなら夏から秋のオス、内子を楽しむなら冬のメスと言うことになりそうです。

ガザミのおすすめの食べ方
カニの仲間はは死んでしまうと、ほぼ例外なく自己消費を始めてしまい、どんどん身が痩せ、鮮度が落ちてしまいますので、生きているものか、水揚げ後すぐにボイルしたり、冷凍したものを選んで下さい。また、大きさだけで判断せず、必ず手に持ってみてズッシリと重みがあるものでなければなりません。
この時期のメスは内子が期待出来ますので、素直に蒸すのが一番出でしょう。茹でるのが簡単ですが、うっかりすると内子が流れ出たり、身が水っぽくなったりするので、注意が必要です。
また、かなり手間がかかりますが、身や内子を一緒に楽しむ料理としてはケジャンもお勧めです。

ケガニ
ケガニはクリガニやトゲクリガニなどと同じクリガニ科のですが、クリガニやトゲクリガニは安価なのに対し、ケガニはオスで甲長15cmと大きくなるため、身がしっかりあることに加え、身やミソの美味しさから高級品として流通しています。
主な産地は、胆振、日高、網走、宗谷、十勝、釧路などの北海道沿岸各地と岩手県です。以前は大量に水揚げがあったとされていますが、今では最盛期の10分の1程度まで減少しているため、各地で厳しい規制が行われています。メスガニ、甲長8cm未満、脱皮直後ののものはリリースされます。加えて、リリース時に傷ついていたりすると死んでしまうため、必ず籠を使って漁をしなければなりません。また、漁が行える船隻数、1隻が使える籠の数、漁期中の水揚げ総量などの制約もあります。
ケガニは冬にになると出回るが増えるようなイメージがありますが、実は1年中どこかで水揚げがあります。それぞれの漁期は、胆振で6~7月、登別から白老町沖で7月中旬から8月中旬、日高で12月~4月、十勝と釧路で1~3月と9~12月、オホーツク沿岸は流氷がなくならない塗料が出来ないため、網走で3~8月、雄武町で3月下旬~7月下旬、宗谷で3月15日~8月21日となります。道外の岩手県では12~3月となっています。
それぞれの産地で、最も身質が良いであろう時期に漁が行われていますので、他のカニ類とは異なり、いつでも美味しいケガニに巡り合うことが出来ます。

ケガニのおすすめの食べ方
カニの仲間はは死んでしまうと、ほぼ例外なく自己消費を始めてしまい、どんどん身が痩せ、鮮度が落ちてしまいますので、生きているものか、水揚げ後すぐにボイルしたり、冷凍したものを選んで下さい。また、大きさだけで判断せず、必ず手に持ってみてズッシリと重みがあるものでなければなりません。高いカニですので、慎重に選びましょう。
新鮮なものはお刺身で食べることも出来ますが、クリガニの仲間は足が短くいので、可食部分はわずかです。やはりお勧めお薦めの食べ方は、茹でるか蒸すかしたものの身やミソをほぐして食べることです。クリガニの仲間は何と言ってもミソが美味しいので、この食べ方が一番でしょう。
もちろん、良い出汁が出ますので汁物にも最適です。また、グラタン、パスタ、サラダ、コロッケなどの洋風料理でも、他の具材に味が負けることなく、ケガニの芳醇な味わいを楽しむことが出来ます。

ズワイガニ
ズワイガニはオスとメスで大きさが違うことや、メスは内子や外子と呼ばれる卵巣や卵を持っていることなどから、産地ではオスとメスを別物として扱っています。価格もオスは高価で、ほとんどが都市部の消費地市場や料理屋へ送られるのに対し、メスは手頃な価格で、産地ではスーパーなどに並ぶこともあります。
また、良く似たものにベニズワイガニとオオズワイガニがいますが、ベニズワイガニとは見た目での判断が容易です。オオズワイガニは国内ではほとんど水揚げがないため、ほぼ100%冷凍加工されてからの輸入です。またオオズワイガニを学名からバルダイ種と呼ぶのに対し、本種はオピリオ種とも呼ばれています。
国産ズワイガニの主な産地は、日本海から北海道沖に集中しており、太平洋側は獲れてもごくわずかです。水揚げが最も多いのは北海道で、次いで兵庫県、鳥取県、福井県、石川県などと続きます。本種は海外でも水揚げがあり、カナダ、アメリカ、ロシアなどでも獲れており、ロシア産はは活物で輸入されることがあります。
国内の漁期は資源保護のため、厳格に定められていますが、全国一斉ではなく産地で微妙にずれています。良くニュースで見る11月初め頃の解禁は富山県以西のもので、メスは1月10日まで、オスは3月20日までです。一方新潟以北では10月1日が解禁日で、オスメスともに5月31日まで漁が続きます。ただメインシーズンは11月から3月くらいまでです。
また、甲の大きさにも制限があり、幅9cm未満のオスと未熟なメスは漁獲禁止となっています。生鮮のズワイガニは、輸入の活物を除き、この期間しか入手出来ませんので、当然漁期が旬となります。
また、各産地で厳格な基準の元、ブランド化が進められており、有名なところでは、石川県の加賀、能登で水揚げされたオスが加能ガニ、石川県内で水揚げされたメスが香箱蟹(メスのブランド化はここだけ)、山形県の庄内に水揚げされるオスが芳ガニ、島根県、兵庫県、京都府の山陰地方で水揚げされるオスが松葉ガニ、京都北部の丹後半島にある間人(たいざ)港で水揚げされるオスが間人ガニなどとされており、適正に流通するよう各産地でタグ付けが行われています。また、等級分けも行っている産地もあり、最上級のものは超高値で取引されています。

ズワイガニのおすすめの食べ方
カニの仲間はは死んでしまうと、ほぼ例外なく自己消費を始めてしまい、どんどん身が痩せ、鮮度が落ちてしまいますので、生きているものか、水揚げ後すぐにボイルしたり、冷凍したものを選んで下さい。また、大きさだけで判断せず、必ず手に持ってみてズッシリと重みがあるものでなければなりません。高いカニですので、慎重に選びましょう。
鮮度の良いものは、お刺身やシャブシャブがまずはお勧めです。こういう食べ方が出来るのはズワイガニならではです。
他は、蒸す、茹でるはもちろん、焼き、天ぷら、鍋、雑炊など多種多様な料理を楽しむことが出来ます。無論、殻からはとても良い出汁が出ますので、全て使い切ることが出来ます。。

ベニズワイガニ
ベニズワイガニは松葉ガニでも知られるズワイガニの仲間で、姿形はそっくりですが、その名の通り加熱しておらずとも既に赤い色になっているのが最大の特徴です。水揚げがズワイガニより多いと言うこともありますが、足が細く、身が水っぽいと言うことなどから、国産ズワイガニの5分の1~10分の1の値段で流通することも多いです。しかし、ミソの旨味や身の甘味はズワイガニより良いと言う評価もあり、とにかくコストパフォーマンスには優れています。
産地としては、鳥取県、島根県、兵庫県、新潟県、石川県など日本海側に集中しており、特に山陰地方で多く水揚げされています。兵庫県では香住漁港にしか水揚げされていないことから、香住ガニと呼ばれており、良いものは漁船の名前が印字された白いタグが付けられてから出荷されます。
ベニズワイガニもズワイガニ同様、資源保護のため各地でサイズ規制や禁漁期間が設定されており、また、メスは全国一律で捕獲禁止とされています。
主な漁期は、鳥取県(境港市)で9~6月、兵庫県(香住)と富山県で9~5月、新潟県と石川県で3~12月、北海道の茂津多岬以北で7~4月、北海道の茂津多岬以南で4~8月と、1年中どこかで水揚げされていますので、いつでも楽しむことが出来ます。

ベニズワイガニのおすすめの食べ方
カニの仲間はは死んでしまうと、ほぼ例外なく自己消費を始めてしまい、どんどん身が痩せ、鮮度が落ちてしまいますので、生きているものか、水揚げ後すぐにボイルしたり、冷凍したものを選んで下さい。また、大きさだけで判断せず、必ず手に持ってみてズッシリと重みがあるものでなければなりません。
鮮度がべらぼうに良い場合はお刺身でも食べることも可能ですが、水分が多いのであまりお勧めはしません。ミソは濃厚で、身の甘味は強いため、特にお勧めするのはシンプルに焼き、茹で、蒸し、汁物などです。また、カニの風味が強く、乳製品などとの相性も良いので、グラタンやクリームコロッケなどもお勧めです。
また、ベニズワイガニは缶詰などでむき身になったものも多く流通していますので、調理の下処理が面倒な時には便利です。

タラバガニ
カニの手足の合計は10本なのですが、タラバガニは見ての通り8本です。実はタラバガニはヤドカリ下目に分類されており、カニではなくヤドカリに近い種類です。ですので、横だけではなく、前に歩くことも出来ます。
日本では 鱈が獲れる場所で一緒に獲れたことから、鱈場蟹(タラバガニ)と、英語圏では足を拡げると1mを超える位大きなものがいることもあるため、KingCrab(カニの王様)と名付けられました。
主な生息域は北太平洋及び北大西洋の寒流域ですが、最近では南半球の寒流域でも確認されています。国内で水揚げがあるのは北海道のオホーツク沿岸のみですが、その量は本当にわずかですので、国内需要を賄うためにアメリカ、ロシア、ノルウェーなどから多く輸入しており、漁場が近いロシアからは活物でも輸入されています。身入りだけ見ると、北海道より寒い海域で獲れている輸入物の方が良いと言う評価もあります。
国内(北海道)の漁期は、おおむね2回に分けられます。ひとつは流氷がなくなることにより漁が再開される3~5月で、この頃は餌が豊富になるため、身が充実し、甘味が増すと言われています。もうひとつは脱皮が終わり身質が向上すると言われている10月~2月です。ただし、10~11月は脱皮直後のものが混じったりしますし、12月以降は冬眠期に入るため活動が鈍ることもあり、水揚げ量は期待出来ません。もちろん、流氷が押し寄せる海域では漁は出来ません。ただし、ロシア産の活物はいつでも入荷しているようですので、北海道の禁漁期間中に活物がある場合は、ほぼ間違いなくロシア産と思って頂ければ良いでしょう。

タラバガニのおすすめの食べ方
タラバガニカの仲間も死んでしまうと、例外なく自己消費を始めてしまい、どんどん身が痩せ、鮮度が落ちてしまいますので、生きているものか、水揚げ後すぐにボイルしたり、冷凍したものを選んで下さい。また、大きさだけで判断せず、必ず手に持ってみてズッシリと重みがあるものでなければなりません。
タラバガニは大きなものが基本であることに加え、身の繊維がしっかりしていますので、非常に食べ応えがあります。鮮度の良いものであればお刺身も可能ですが、お勧めは素直に、茹でガニと焼ガニです。濃厚な味わいとしっかりした食べ応えはタラバガニの最大の特徴です。
尚、タラバガニのミソは、そのまま加熱してしまうと流れ出てしまうため、調理する前に取り除いておいて、足などとは別に調理する必要があります。

カミナリイカ
カミナリイカはコウイカの仲間で、唇ともコーヒー豆とも獲れるような紋様が最大の特徴であることから、紋甲イカ(モンゴウイカ)と呼ばれることもあります。カミナリと言う一風変わった名前の由来は、雷の鳴る夏に獲れるからと言う説や、甲の紋様が雷に見えるからという説などがありますが、どちらもかなり無理があるようで、はっきりわかっていません。
カミナリイカは、国内で獲れるコウイカの中では大型で、大きなものは40cmくらいになります。
主に西日本で水揚げされていますが、まとまって獲れるわけではないので、主だった産地と言うのはありません。また、決まった漁期があるわけでもなく、晩冬から夏にかけて産卵のために沿岸によって来たものが他の魚と共に混獲されるくらいです。

カミナリイカのおすすめの食べ方
コウイカの仲間は、鮮度が落ちるにしたがって背側の紋様がぼやけて、最後には白っぽくなります。こうなるとお刺身では少し厳しくなりますので、出来るだけ紋様が鮮やかなものや、表面の細かい斑点が点滅しているものを選びましょう。むき身になっている場合は、張りがあって、透明感のある物を選んで下さい。また、コウイカの仲間は身に付いている薄皮をきちんと取っておかないと口当たりが悪くなることに加え、臭みも残りますので、注意して下さい。
カミナリイカの身は他のコウイカと比べると、少し硬めですので、どのような調理をするにしても食べやすいように細かく切れ目を入れておくと良いでしょう。
甘味が強いイカですので、鮮度が良いものは、まずはお刺身がお勧めです。イカ全般に言えることですが、料理の材料としては万能で、身だけでなく、耳や下足も含め、焼物、炒め物、揚物、和え物などなんにでも合わせることが出来ます。
また、産卵期が近づくと白子が入っている場合があります。見つけたら塩でよく揉み洗いして、焼物、煮物、揚物などにすると美味しく頂くことが出来ます。

コウイカ
コウイカは墨を沢山持っており、水揚げした時に大量にこれを噴くため墨烏賊(すみいか)とも呼ばれます。また、胴のてっぺんに甲の先が針状に突き出していることから、針烏賊(はりいか)と呼ばれることもあります。背側には横縞模様が入っており、オスの方が明確で、メスはぼんやりしているものが多いとされています。産卵期のオスには白子が入っていることが多いので、選ぶ時の目安にして下さい。
主な産地としては、瀬戸内海沿岸や九州などですが、特にここが多いと言うところはありません。
コウイカは産卵のため内湾に集まってくる春から初夏に多く漁獲されますが、産卵後には死んでしまうため、新子が出回るまで目にすることがなくなります。したがって、成魚に関しては産卵前の冬から春先が旬となります。また、晩夏から秋には生まれて間もない5cmくらいのものが獲れます。これは「新イカ」と呼ばれており、身が柔らかく瑞々しいことから珍重され、かなりの高値で取引されます。

コウイカのおすすめの食べ方
コウイカの仲間は、鮮度が落ちるにしたがって背側の紋様がぼやけて、最後には白っぽくなります。こうなるとお刺身では少し厳しくなりますので、出来るだけ紋様が鮮やかなものや、表面の細かい斑点が点滅しているものを選びましょう。むき身になっている場合は、張りがあって、透明感のある物を選んで下さい。また、コウイカの仲間は身に付いている薄皮をきちんと取っておかないと口当たりが悪くなることに加え、臭みも残りますので、注意して下さい。
コウイカは寿司ネタとしてもお馴染みで、高級品として取り扱われることが多いです。コウイカの中では最もお刺身に向いているとされていますが、加熱しても身が硬くなりにくいので、耳や下足も含め、焼物、炒め物、揚物、和え物などなんにでも合わせることが出来ます。墨はイタリアンではお馴染みで、パスタやリゾットなどに使われます。

シリヤケイカ
とんでもない名前を付けられたものですが、その由来は、胴の先端が尖っておらず、お尻のような形をしていおり、そこから赤褐色の粘液を吐き出すこともあることから、先端が赤く染まていることで、尻が焼けたように見えることからと言われています。また、背側にはゴマのような白く小さな斑点のような模様が入っているのも特徴のひとつです。
他のコウイカと同様に春~夏の産卵に向けて内湾に集まってきますので、その頃に他の魚に混じって水揚げがある程度増えますが、身が充実していのは産卵前の秋~春先です。
主な産地としては、東京湾、大阪湾、瀬戸内海などがありますが、どこかが突出して多いと言うことはありません。

シリヤケイカのおすすめの食べ方
コウイカの仲間は、鮮度が落ちるにしたがって背側の紋様がぼやけて、最後には白っぽくなります。こうなるとお刺身では少し厳しくなりますので、出来るだけ紋様が鮮やかなものや、表面の細かい斑点が点滅しているものを選びましょう。むき身になっている場合は、張りがあって、透明感のある物を選んで下さい。また、コウイカの仲間は身に付いている薄皮をきちんと取っておかないと口当たりが悪くなることに加え、臭みも残りますので、注意して下さい。
シリヤケイカは、カミナリイカやコウイカと比べると甘味が足りないとされており、やや低評価のため低価格で流通していますが、同時に食べ比べでもしない限りその違いは分からないレベルですので、そこまで気にする必要もないと思われます。
他のコウイカ同様に、鮮度が良いものはまずはお刺身がお勧めで、もちろん、耳や下足も含め、焼物炒め物、揚物、和え物などなんにでも合わせることが出来ます。墨はイタリアンではお馴染みで、パスタやリゾットなどに使われます。

ジンドウイカ
ジンドウイカは大きくても胴長10cm程度の小さなイカで、ヒイカとも呼ばれています。
ほぼ全国で水揚げがあり、東日本では宮城県などの三陸から房総沖、中部では三河湾から伊勢湾、西日本では和歌山県や瀬戸内海周辺などで見られます。
市場には周年出荷されているようですが、小さいこともあり品質や味のバラツキが大きなことが原因なのか、値段が高いわけでもないのに、何故かスーパーなどに並ぶことは少なく、料理屋でもあまり見かけることのない、非常にマイナーな存在です。
水揚げが増える時期も産地でかなりばらついており、春から夏というところや、冬から春にかけてというところに分かれます。共通しているのは、晩夏から初冬は水揚げが減るところです。

ジンドウイカのおすすめの食べ方
生きているものは内臓が透けて見えるくらいの透明感がありますが、時間経過とともに赤みを帯び、さらに透明感のない白濁色になります。特にこのイカは小さいこともあって、鮮度劣化が早いので、最低でも多少なり赤みが残っている物を選んで下さい。
鮮度が良ければお刺身がお勧めで、もし生きているものが手に入れば歯応えを楽しむことが出来ます。
加熱調理する場合は、小さいので、特に処理する必要もなく、軽く火を通す程度で十分です。

ソデイカ
ソデイカも多くのイカと同様には1年魚なのですが、大きなものは胴長1m、重量30kgにもなります。あまりにも大きすぎるため、冷凍の柵などでの流通が大半で、産地でもない限り丸のまま見る機会はまずないでしょう。
名前の由来は、第三腕に付いているヒレ状の幕が袖の様に見えることですが、地方によっても様々な名前があり、兵庫県から鳥取県の山陰地方ではアカイカ(標準和名でアカイカと言う別種あり)、京都府から石川県ではタルイカ、沖縄県ではセーイカと呼ばれています。など、地方によって様々な呼び名があります。
産卵期も産卵場所も特に決まっておらず、暖海域であればほぼ1年中いたるところで産卵していますので、ほぼ1年中どこかで水揚げがあります。
主な産地は兵庫県、鳥取県、福井県、鹿児島県、沖縄県ですが、中でも沖縄県が抜きん出ており、県のプライドフィッシュにも指定されています。
沖縄県では、毎年変更されますがおおむね7~10月が禁漁期間となっており、2~3月が最盛期となります。一方、日本海沿岸では6月頃から若い個体が獲れ始め、最盛期は9~11月となります。

ソデイカのおすすめの食べ方
丸のままで入手出来たとしても、大きさによっては一家庭で食べ切れなくなりますので、柵などに切り分けられたものを購入した方が無難です。生鮮の場合、赤みがかったものは鮮度が落ちている可能性がありますので、綺麗な白色のものを選んで下さい。また、生鮮のままだと、身が硬く、大味で旨味が足りないため、面倒でも一度冷凍するか、冷凍したものを購入されることをお勧めします。そうすることにより、甘味が増すとともに、もっちりとした食感になり、加熱してもそう硬くはなりません。
料理用途は、お刺身はもちろんん、焼物、煮物、炒め物、揚物など多種多様ですが、大きな切身にする場合は食べやすくするために、切り込みを入れておいた方が良いでしょう。

ホタルイカ
ホタルイカは胴長7cm、重量10g程度の小さなイカで、腕や腹部に沢山の発光器を持ち、蛍と同じように青白く光ることが名前の由来です。
日本海側一帯や、駿河湾、相模湾などで生息が確認出来ていますが、商業漁業が可能な水揚げがあるのは富山県、兵庫県などに限られます。
ホタルイカは富山湾が有名ですが、水揚げが最も多いのは兵庫県の日本海側で、その次が富山県です(とは言っても、この2県くらいしかないのですが)。漁法は異なり、兵庫県では日中の底曳網漁を行うのに対し、富山県は夜間の定置網漁です。兵庫県で獲れるものは、底曳網漁のため鮮度保持が難しく、ほぼ全てが水揚げ後すぐに釜茹でされてしまいますが、富山県では生はもちろん、活物でも出荷出来ますので、評価が高くなっています。
また、富山県では乱獲防止のため、富山市水橋から魚津市にかけての海岸沿い約15km、沖合約1.3kmの海域は、春にホタルイカの群れが押し寄せることから「ホタルイカ群遊海面」として国の特別天然記念物に指定されています。
漁期は、兵庫県で1月下旬頃に解禁となり、3~4月が最盛期を迎え、5月末まで続きます。富山県は毎年3月1日が解禁日で、最盛期は4~5月初旬頃で、6月末まで続きます。身質が最も良くなる時期はいずれの産地も3月頃から4月と言われています。

ホタルイカのおすすめの食べ方
1~2月のものは兵庫県産で、ほとんどが釜茹でにされて流通しています。そのまま食べても良いのですが、冷蔵流通のため味が分からなくなるくらい冷えていることもありますし、梱包の甘いものはホタルイカが汚れてしまうこともありますので、念のため軽く洗ってから、再加熱した方が無難です。お勧めは酢味噌和え、煮物、揚物、炊き込みご飯などです。また、小さくても目や口は他のイカ同様に硬いので、気になる場合はあらかじめ取り除いておきましょう。
生でそこそこ鮮度が良いものが手に入ったとしても、ホタルイカには旋尾線虫と言う寄生虫がいることが多く、これは人にも寄生します。魚体も寄生虫も非常に小さいので完全に取り除くことは極めて難しいため、いくら鮮度が良くても生食は止めておきましょう。
※旋尾線虫は人体内部では成長しませんが、幼体のまま胃腸を破って腹部の皮膚近くに移動し、ミミズ腫れなどの症状を引き起こしたり、腸付近に留まるとと腸閉塞を起こしたりします。冷凍で死滅させる方法もありますが、その温度はー30℃以下ですので、家庭用冷蔵庫では不可能です。

ヤリイカ
ヤリイカの名前は、胴が細長く先が鎗のように尖っていることに由来します。良くケンサキイカに似ていると言われますが、ケンサキイカと比べると胴長短足のため、並べてみると違いははっきりします。ただし、ヤリイカは冬場の水揚げが多く、ケンサキイは春から夏の水揚げが多いため、並べて比較する機会はそう多くありません。また、価格的にはスルメイカより高く、ケンサキイカより安い中間的な立ち位置です。
日本全国で水揚げがあり、主な産地も、北海道、青森県、宮城県、長崎県など広範囲です。水揚げが増えるのは、産卵のため接岸して来る冬から春にかけてで、この時期のものは子持ちとなります。

ヤリイカのおすすめの食べ方
生きているものは半透感ですが、表皮は次第に鮮やかな赤色となり、さらに鮮度が落ちてくると茶褐色となり、身は白濁します。お刺身にする場合は、鮮やかな赤色までのものを選んで下さい。
お刺身にした場合、身は柔らかめで適度な歯応えがあります。甘味はケンサキイカほど強くありませんが、上品な味わいを楽しむことが出来ます。また、一度冷凍すると甘味が増すと言われていますが、身の透明感は失われます。
加熱しても硬くなりにくいので、炒め物、揚物などにも向きます。また、子持ちで小振りなものが手に入った場合は、素直に煮付けにした方が良いでしょう。

イイダコ
イイダコは漢字で飯蛸と書くように、子持ちのメスを煮た時に、胴に詰まっている卵が飯粒のように見え、また、その食感も飯粒のようだと言うことに由来すると言われています。
イイダコの大きな特徴は、両目の間に菱形または長楕円形の白い斑紋があること、左右第2腕と第3腕の付け根に金色の輪紋があることです。また、タコの仲間では小さな部類に入り、大きくなっても、メスで全長30cm程度、オスで25cm程度です。
産地は内湾に面したところが多く、主だったところでは、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県などの瀬戸内海沿岸、愛知県など三河湾沿岸、福岡県、佐賀県、熊本県など有明海沿岸などが挙げられます。水揚げは産卵期に当たる1~4月上旬に増えます。実は1年中水揚げが確認されてるのですが、量が少なく、市場流通するには至っていません。

イイダコのおすすめの食べ方
タコ全般に言えることですが、鮮度が悪くなると白っぽくなってしまいますので、なるべく体色が濃く、金の輪紋や両目の間の白い斑紋が明瞭なものがを選んで下さい。ただし、産卵期のオスは白っぽいので、色で判断しにくい場合は、触ってみた時に、表皮の色が変わる物や、吸盤が手に吸い付いてくるようなものを選ぶと良いでしょう。また、砂泥地に生息しており、底曳網で漁獲されることが多いため、吸盤などに泥や砂を噛んでいることが多いので、調理前にはしっかりと洗って下さい。
この時期のイイダコは、子持ちとそうでないものに区別され流通しており、子持ちで鮮度の物は良いのものは高値で流通します。ただし、高いからと言って、必ずしも卵がパンパンに詰まっているわけではありませんので、出来れば胴がパンパンに膨らんでいるものを選んで下さい。
小さいタコですので、いくら鮮度が良くても生のままお刺身に加工するのは至難の業ですので、止めておいた方が無難です。子持ちが手に入った場合は、何を置いても煮物がお勧めです。甘辛く煮付けた身と、プチプチした食感で淡い味わいの卵の組み合わせはこの時期しか味わうことが出来ません。子を持っていないものやオスを煮付けにしても十分美味しいのですが、身の旨味をしっかり味わうためには、あまり濃い味付けにはせず、酢味噌和え、揚物、炊き込みご飯などにすると良いでしょう。

アカガイ
アカガイは、貝の中では珍しく、血液に人と同じようにヘモグロビンを含んでいるため、その色は赤く、名前の由来にもなっています。
大きなもので殻長10~12cm程で、殻の表面に放射状の縦溝が42~43本(良く似たサルボウガイは32本、サトウガイは38本)あり、縁を中心に全体が茶色い毛で覆われています。また、厚みもあり、大きなものでは殻高が8~9cmにもなります。
産地としては、三陸、東京湾、三河湾、伊勢湾、瀬戸内海、有明海などがありますが、その量は年々少なくなっており、中国や韓国から活物やむき身の状態で輸入されるものの割合が増えています。生鮮のアカガイは、以前は身近な食材だったのですが、今では輸入品でさえも高級品になってしまいました。
産卵期は海域で異なり、西日本では5~6月頃、三陸周辺では7~8月頃で、この期間は各地で禁漁となっていますが、どこかしらで水揚げがあるため、ほぼ1年中姿を見ることが出来ます。しかし、美味しい時期となると、産卵後に再び身が充実してくる冬から春先までとなります。

アカガイのおすすめの食べ方
貝全般に言えることですが、殻付きの場合は、必ず元気よく生きているものを選びましょう。また、2枚貝は砂泥地に生息していることが多く、元気が良くても泥臭い場合がありますので、臭いがないことも確認しておく必要があります。また、稀に中身がほとんどないと言ったようなものもありますので、持った時にズッシリと重みがなければなりません。むき身の場合は赤身が強く、肉厚のものを選びましょう。
加熱しても美味しい貝ですが、気楽に食べられる値段ではないので、やはりお刺身にせざるを得ないでしょう。ヒモ(外套膜)もきちんと処理すれば、美味しく頂くことが出来ます。
※2枚貝は時期(おおむね春から夏)により自然毒(貝毒)を持つ場合がありますので、ご自分で採取される場合は、必ず各自治体の発表を確認し、該当する時期の採取は行わないで下さい(市場流通しているものは問題ありません)。また無許可の採取は罰せられる場合があります。

サルボウガイ
サルボウガイもアカガイの仲間で、血液に人と同じようにヘモグロビンを含んでいるため、赤い色をしています。見た目もアカガイにそっくりですが、殻長は4~6cmとアカガイの半分程度で、殻の表面に放射状の縦溝は32本(アカガイは42~43本、サトウガイは38本)と言うところで区別出来ます。
貝の膨らみが猿の頬に似ているため、猿頬貝(サルボウガイ)と名付けられたと言われていますが、標準和名で呼ばれることはあまりなく、チガイ、コアカ、モガイ、ハイガイなど、産地の数だけ地方名があるくらい様々な名前で呼ばれています。山陰でアカガイと呼ばれたり、缶詰の味付赤貝の原料となっていることなど、紛らわしい面もあります。以前はむき身を刺身用に加工して、アカガイと称して販売していたこともありましたが、現在では法令で禁止されています。
主な産地は、東京湾、山陰沿岸、瀬戸内海、有明海などの内湾の干潟で、岡山県の寄島町海域では栽培もおこなわれています。ほとんどが産地か、産地間で取引されてしまうため、生鮮で馴染みのない消費地へ出回ることはまずありません。
サルボウガイの産卵期は夏なので、身が美味しくなるのは冬から春にかけてとなります。

サルボウガイのおすすめの食べ方
貝全般に言えることですが、殻付きの場合は、必ず元気よく生きているものを選びましょう。また、2枚貝は砂泥地に生息していることが多く、元気が良くても泥臭い場合がありますので、臭いがないことも確認しておく必要があります。また、稀に中身がなく泥が詰まっているということもあります(俗に爆弾と呼ばれています)。これが混じったまま調理すると、最悪の場合、料理全体にヘドロやヘドロ臭が付いてしまうので注意が必要です。大体は出荷元で除去されていますが、すり抜けてくる場合もありますので、面倒でも5~6個くらいずつ手に持って、音で確認するくらいしか方法がありません。乾いた高い音がすれば中身は空っぽで、反対に妙に重たい音がすると泥が詰まっている可能性が高くなりますので、包丁などで開いて確認した方が良いでしょう。選別が終わったら、しばらく活かし込みをして砂出しをします。
鮮度が良ければ、アカガイ同様にお刺身にも出来ますが、小さい分かなりの手間が必要ですので、あまりお勧めは出来ません。産地ではそのまま甘辛く煮つけたり、身だけを佃煮などにすることが多いので、その食べ方が一番無難と言えるでしょう。また、岡山県ではバラ寿司の重要な具材のひとつで、年末年始には欠かせない食材のひとつになっています。
※2枚貝は時期(おおむね春から夏)により自然毒(貝毒)を持つ場合がありますので、ご自分で採取される場合は、必ず各自治体の発表を確認し、該当する時期の採取は行わないで下さい(市場流通しているものは問題ありません)。また無許可の採取は罰せられる場合があります。

エゾアワビ
エゾアワビは見た目も食感もクロアワビによく似ています。足の色はクロアワビと同じような黒っぽいものからクリーム色のものまで個体差があり、比較的明るい色のものが多いとされています。また、流通しているものは、クロアワビより小さなものが多くいです。養殖もされており、韓国や中国から活物や冷凍で輸入されています。
エゾアワビは養殖されていることもあり、ほぼ周年市場流通しています。また、アワビと言うと夏のイメ-ジが強いのですが、エゾアワビの産卵期は8~10月ですので、身質が良いのは産卵前の初夏と、晩秋から冬になります。流通が増えるのは、年末年始需要があるため11~1月となります。

エゾアワビのおすすめの食べ方
貝全般に言えることですが、殻付きの場合は、必ず元気よく生きているものを選びましょう。また、アワビは身がむき出しで生活していますので、調理時にしっかり洗って汚れを落としておきましょう。貝殻を皿などに再利用する場合は、煮沸消毒した後、しっかり洗って汚れを落として下さい。
エゾアワビはコリコリした食感が特徴ですので、一般的には生のお刺身を好む傾向がありますが、火を通すことにより柔らかくなり風味も増しますので、焼物、煮物、蒸し物などもお勧めです。
※2~5月頃のアワビの中腸線に餌となる海藻のクロロフィルに由来する毒素が溜ることがあり、これを大量に食べると極まれに光過敏症という中毒を起こすことがあります。有毒な中腸腺は黒っぽい濃い緑色なのに対し、無毒な物は灰緑色か緑褐色なので、色で見分けられるそうですが、念のため同時期のアワビの肝は避けた方が良いでしょう。また、無許可の採取は禁止されています。

ヒオウギガイ
ヒオウギガイの最大の特徴は、人工的に着色したかのような鮮やかな色で、個体によって黄色、オレンジ、紫、赤などに分かれており遺伝します。ヒオウギガイはほとんどが栽培されており、綺麗な色の親貝を選抜し人口採卵するため、市場に出待っているものは鮮やかな色のものが目立ちます。紫や赤は冠婚葬祭などの料理に、また、飾り物や器としての利用価値も高い貝です。ちなみに、天然物は褐色の割合が多いと言われています。殻の色に目を奪われがちですが、身はホタテより甘味が強いと言われており、評価はとても高いです。
上述したように、市場流通しているもののほとんどは栽培物で、産地としては、愛媛県の愛南町、三重県志摩、熊本県天草、大分県佐伯市、島根県隠岐などがありますが、生産量は決して多い訳ではありませんので、スーパーなどに並ぶことは滅多にまずありません。
人口採卵するためか、産卵期に当たる4~5月と、産卵明けで身が痩せている夏の出荷はほとんどありません。美味しい旬の時期は、産卵が空けて再び身が充実する晩秋から、産卵前の春までとなります。

ヒオウギガイのおすすめの食べ方
貝全般に言えることですが、殻付きの場合は、必ず元気よく生きているものを選びましょう。ヒオウギガイは栽培が主体ですので、砂を噛んでいることはほとんどありませんが、気になる場合は、むき身にしてから良く洗っておくと良いでしょう。また、貝殻を皿などに再利用する場合は、煮沸消毒した後、しっかり洗って汚れを落として下さい。
鮮度が良いものはお刺身での良いのですが、この貝は加熱することでさらに甘味が増すと言われていますので、焼物、煮物、揚物などがお勧めです。また、少々加熱しても硬くなりにくいので、炊き込みご飯、グラタン、ピザなどにも適しています。
※2枚貝は時期(概ね春から夏)により自然毒(貝毒)を持つ場合がありますので、ご自分で採取される場合は、必ず各自治体の発表を確認し、該当する時期の採取は行わないで下さい(市場流通しているものは問題ありません)。また無許可の採取は罰せられる場合があります。

ホタテガイ
ホタテガイは食用の貝としては最も一般的と言っても良いくらい普及しており、生鮮、冷凍、ボイル、貝柱など様々な形態で全国に流通しています。
大きくなると殻長20cmを超えることもあり、表裏で色や形が違うのも特徴です。表側は少し丸く膨らんでおり白っぽく、裏側は平らに近く紫褐色となっています。
市場に流通しているものには栽培物と天然物がありますが、100%天然は少なく、そのほとんどは稚貝を放流してから約3年後に収穫したものです。厳密には天然とは言えないかも知れませんが、川に放流した魚と違って、数年は自活しているわけですので、天然と言っても全く差支えはないでしょう。
撒くための稚貝の採取は、幼生が生活のために岩などに付着する習性を利用しています。産卵期である春に生息域に採苗器を沈めてから幼生が自然に付着するのを待ちます。その後、おおむね1cm程度に成長したであろう時期に引き上げて、稚貝を採取します。この後、1年程度生育し、海に撒くか、栽培するかに分けます。
産地は北海道と青森県でほぼ100%を占めています。天然物はほぼ100%北海道で、栽培物は約60%が青森県で、残り約40%が北海道です。岩手県や宮城県でも採取が行われていますが、その量は本当にわずかです。
青森県はベビーホタテと呼ばれる小さなものが有名です。籠の中が過密になると生育が阻害されるため、半成貝と呼ばれる5cm程度のものを4~6月くらいに間引いて出荷します。2~3年育ててある程度大きくなったものは、基本的に1年中水揚げがありますが、多いのは2~8月のようです。北海道では、栽培物は3~4月、撒いたものは8~9月の水揚げが多いとされています。
美味しい旬の時期は水揚げ時期とは少し異なりますが、産卵に向けて生殖巣が最も大きくなるのは冬ですので、生殖巣を一緒に食べるのであれば冬が美味しいと言うことになります。ただし、貝柱だけで見ると産卵後に栄養が回復する夏が良いと言えるでしょう。

ホタテガイのおすすめの食べ方
貝全般に言えることですが、殻付きの場合は、必ず元気よく生きているものを選びましょう。栽培物の場合は、砂を噛んでいることはほとんどありませんが、天然物の場合は砂を噛んでいることが多々あります。念のため、いずれであっても、むき身にしてから良く洗っておくと良いでしょう。また、貝殻を皿などに再利用する場合は、煮沸消毒した後、しっかり洗って汚れを落として下さい。
冬場は生殖巣が発達している時期ですので、貝全体を味わう季節ですので、素直に焼物などにした方が良いでしょう。
2枚貝にはウロと呼ばれる黒っぽく丸い中腸線などの内臓が付いており、特にイタヤガイの仲間は目につきます。大きな貝であれば、貝毒の危険を避けるため取り除いた方が良いのですが、小さなものであれば、特に気にする必要はありません。
※2枚貝は時期(おおむね春から夏)により自然毒(貝毒)を持つ場合がありますので、ご自分で採取される場合は、必ず各自治体の発表を確認し、該当する時期の採取は行わないで下さい(市場流通しているものは問題ありません)。また無許可の採取は罰せられる場合があります。

ウバガイ
ウバガイは、ホッキガイとして流通することが非常に多く、標準和名では通じないこともあるようです。ホッキガイと言う名前はアイヌ語が語源とされており、ウバガイと言う名前は、この貝が30年以上と長生きすることから、年老いた女を意味する姥(うば)が付けられたとされています。
この貝の仲間は海外にも多く棲息しており、日本には特にカナダからボイル加工されたものが多く輸入されています。スーパーや回転寿司などに並ぶものはほとんどがカナダ産ですので、口にする機会は国産の比ではないでしょう。ちなみに、カナダ産のものはカナダホッキガイと呼ばれており、カナダウバガイではありません。
国内の主な産地は、北海道を筆頭に、福島県、青森県などの北日本に集中していますが、その中でも苫小牧市での水揚げが多く、平成14年には「苫小牧市の貝」として制定されています。ただし、資源量は決して多くありませんので、各漁協ごとに厳しく漁が規制されており、産卵期に当たる晩春から夏はほぼ禁漁となっています。
禁漁期間を除けば、少ないながら水揚げはありますが、美味しい旬の時期は産卵期前の冬から春にかけてとなります。

ウバガイのおすすめの食べ方
貝全般に言えることですが、殻付きの場合は、必ず元気よく生きているものを選びましょう。ウバガイも砂を噛んでいることがありますが、砂を吐かせるのはかなり難しいことに加え、食用部位は、斧足、海馬下、ヒモの部分だけですので、むき身にしてから良く洗えば問題ないでしょう。
鮮度が良いものであれば、まずはお刺身がお勧めです。お店などでは斧足が赤くなっていることがありますが、これは加熱したためであって、生の状態ですと黒ずんでいます。いずれが美味しいかは個人差がありますが、一般には、軽く火を通した方が甘味が増すとされており、見た目も良くなります。また、決して安くない貝なので、少しもったいないですが、加熱しても硬くなりにくいので、焼物、煮物、揚物、炒め物など、色々な料理にも使えます。
※2枚貝は時期(おおむね春から夏)により自然毒(貝毒)を持つ場合がありますので、ご自分で採取される場合は、必ず各自治体の発表を確認し、該当する時期の採取は行わないで下さい(市場流通しているものは問題ありません)。また無許可の採取は罰せられる場合があります。

ツブガイ(総称)
ツブ、またはツブガイと言う標準和名の貝は実際にはおらず、これはエゾバイ科の中で食用にされているもの総称として使用されています。ざっくりですが、エゾバイ科の中でもエゾボラ属をツブガイと呼び、それ以外はバイガイと呼ぶ事が多いようです。しかし、地方によりツブガイのことをバイガイと呼んだり、その逆もあったりするなど本当に様々ですので、実物を確認して判断するしか方法がないのが実情です。ここではエゾボラ属の貝類をツブガイとして紹介します。
市場に出荷されるツブガイで比較的流通が多いのは、マツブと呼ばれるエゾボラです。これはツブガイの中では最も大きく、味の評価も高く、最も高値で取引されています。その他には、エゾボラモドキ、チヂミエゾボラ、ウスムラサキエゾボラ、ウネエゾボラなどがありますが、専門家でもない限り区別するのは難しいため、まとめてツブガイとして流通しています。こちらは小さなこともあってか、刺身に使い肉などの理由から、エゾボラよりかなり安いのですが、味がそこまで違うかと言われると微妙な範囲ですので、かなりお買い得です。
産地としては、北海道が飛びぬけています。本州の日本海沿岸や三陸沿岸でも見られますが、その量はわずかです。
産卵期は冬から夏にかけてと言われていますが、資源がある程度見込めるためか漁は1年中行われています。旬は地域によって言い分があり、日高地方から稚内周辺は4~9月、十勝周辺は12~4月頃と言われていますが、正直大きな違いはなさそうです。

ツブガイのおすすめの食べ方
貝類全般に言えることですが、殻付きの場合は元気に生きているものを選びましょう。また、手に持った時にズッシリと重みを感じるものであることはもちろん、特にツブガイの場合は、出来るだけ大きなものがお勧めです。これは、調理が容易になることに加え、味わいも良いとされることが理由です。
大きなものは何と言ってもお刺身がお勧めで、サザエのようにコリコリした食感で、程よい磯の風味と旨味を感じることが出来ます。小さなものは、焼物、煮物、和え物、炒め物などにすると美味しく頂けますが、加熱すると硬くなってしまいますので、軽く火を通す程度にしておきましょう。
※エゾボラ属の貝には唾液腺の部分に人の神経を麻痺させるテトラミンという有毒成分が含まれており、これは加熱しても分解されませんので、必ず取り除いて下さい。取り除くのが難しい場合は、取り除いたものを必ず購入して下さい。また、無許可の採取は罰せられる場合があります。

マガキ
日本にはおよそ25種類のカキが生息しているそうですが、食用にされているのは主に、マガキ、イワガキ、スミノエガキ、それに絶滅の懸念があるイタボガキガキなどです。そのうちマガキは、栽培が積極的に行われているため、圧倒的な割合を占めており、普通カキと言えばマガキを指します。
マガキは産卵期には身が痩せてしまうため、産卵期である夏前後の出荷は行っていません。また、鍋など寒い時期の料理が定着していることもあってか、冬の食材として定着しており、冬を旬とするのが一般的で、この時期水揚げがピークを迎えます。
産地は、太平洋側、瀬戸内海などの内湾に集中しており、外洋や日本海側には見られません。自治体別では、広島県が最も多く全体の60%以上を占め、次いで宮城県が10%程度、その他岡山県、兵庫県などと続きますが、いずれも一桁です。
各地で様々なブランド化も進められており、栽培方法や味わいも様々ですので、機会があれば取り寄せて楽しむのも良いでしょう。

マガキのおすすめの食べ方
殻付きで買われる場合は、必ず口がきちんと閉まっているものを選びましょう。口が空いたままのものは、死んでいる可能性があるので避けましょう。また、持ってみてズッシリとした重みのあるものが良いです。殻付きの場合は、むき身にしてから、汚れなどを落とすための洗浄を行って下さい。ただし、焼きガキなどにして、すぐに食べる場合は、そこまで神経質になる必要はないでしょう。
マガキは塩水入りのむき身で流通することが多いので、必ず水が濁っていないものを選びましょう。水が濁っていると、鮮度が悪くなっている可能性が高くなります。また、必ず生食用か加熱用かの記載を確認してから調理して下さい。殻付きで生きているものであっても、生食用と記載のないものの生食は自己責任です。
マガキはどのような料理にも対応できる万能選手ですので、これが特にお勧めと言うものはありません。焼物、煮物、鍋物、揚物、炒め物、炊き込みご飯など、その時に食べたいものに合わせて調理して頂ければ良いでしょう。
※2枚貝は時期(おおむね春から夏)により自然毒(貝毒)を持つ場合がありますので、ご自分で採取される場合は、必ず各自治体の発表を確認し、該当する時期の採取は行わないで下さい(市場流通しているものは問題ありません)。また無許可の採取は罰せられる場合があります。

シジミ(総称)
国内に生息しているシジミは、ヤマトシジミ、マシジミ、セタシジミなど3種ですが、細かく名称を分けることなく全てシジミとして流通しています。
このうちヤマトシジミは国内で最も一般的なもので、北海道から九州に至るまで全国の河口などの汽水域の砂礫底に生息しています。マシジミとセタシジミは淡水性ですが、農薬や河川護岸工事などの影響から、今ではほとんど姿を見ることが出来なくなっており、国産で流通するシジミの99%はヤマトシジミだと言われています。
また、国産で賄えきれない場合は、中国や台湾から活物で輸入されることもあります。こちらも違う種類ですが、国産シジミが生息する流域で活かし込みなども行われているため、種の交雑が懸念されるところです。
ヤマトシジミの産地としては、青森県の十三湖と小川原湖、島根県の宍道湖、茨城県の涸沼川と利根川、北海道の網走湖とパンケ沼などがあります。セタシジミは滋賀県の琵琶湖で僅かながら水揚げが確認出来ますが、マシジミは漁業としては成立していないようです。
シジミは周年通水揚げがあり、流通も安定しているため、旬を感じにくい食材にひとつになっていますが、美味しい時期については、一般的には、夏を旬とする「土用蜆」、冬を旬とする「寒しじみ」があります。また、産卵期が夏であるため、これに備えて栄養を蓄える春が良いと言う説もあります。身の充実を考えると春とするのが一般的ですが、昔から夏と冬に欠かせないものになっているので、いずれも旬として捕らえざるを得ないでしょう。

シジミのおすすめの食べ方
貝全般に言えることですが、殻付きの場合は、必ず元気よく生きているものを選びましょう。また、ヤマトシジミは砂泥地に生息していることが多く、元気が良くても泥臭い場合がありますので、臭いがないことも確認しておく必要があります。加えて、稀に中身がなく泥が詰まっているということもあります(俗に爆弾と呼ばれています)。これが混じったまま調理すると、最悪の場合、料理全体にヘドロやヘドロ臭が付いてしまうので注意が必要です。大体は出荷元で除去されていますが、すり抜けてくる場合もありますので、面倒でも10個くらいずつ手に持って、音で確認するくらいしか方法がありません。乾いた高い音がすれば中身は空っぽで、反対に妙に重たい音がすると泥が詰まっている可能性が高くなりますので、包丁などで開いて確認した方が良いでしょう。選別が終わったら、しばらく活かし込みをして砂出しをします。
また、そのまま調理するより一旦冷凍すると、旨味が増すと言われておりますので、試してみても良いでしょう。
シジミは大きくても殻長2cm弱と非常に小さな貝ですので食べるのが正直面倒です。出汁だけ飲んで、身は食べないと言う人もいるようですが、身には旨味だけではなく、栄養成分もたっぷり詰まっていますので、しっかり食べるようにしたいものです。
簡単で美味しいのは料理と言えば味噌汁ですが、酒蒸し、バター醤油などもお勧めです。身を取り出すのが少々面倒ですが、佃煮や炊き込みご飯などもお勧めです。
※2枚貝は時期(おおむね春から夏)により自然毒(貝毒)を持つ場合がありますので、ご自分で採取される場合は、必ず各自治体の発表を確認し、該当する時期の採取は行わないで下さい(市場流通しているものは問題ありません)。また無許可の採取は罰せられる場合があります。

タイラギ(総称)
タイラギは大きな二等辺三角形のような特殊な形をしている2枚貝です。尖った方を海底の砂地に差し込んだように立って見えることからタチガイと呼ばれたりもしています。
タイラギは1種類のように思われる方も多いよですが、実は複数種おり、殻の表面に細かい鱗片状突起が見られる有鱗型、殻の表面がつるっとしている無鱗型、どちらにも属さないもの、更には有鱗型と無鱗型の交雑種などもあります。有鱗型はケンタイラギ、またはリシケタイラギと呼ばれ、無鱗型はタイラギ、またはズベタイラギと呼ばれていますが、見た目も味もそう変わることがないためか、市場では区別することなく流通しています。
産地としては、瀬戸内海の播磨灘、備讃瀬戸、伊予灘などが有名です。かつては有明海や三河湾などの内湾でも沢山採れていましたが、開発などの環境変化などから激減し、2012年には準絶滅危惧種に指定されています。加えて、味覚の良さも相まって高値で取引されることが多く、スーパーなどで見かけるのは産地か、韓国などからの輸入に限られており、多くは料理屋、寿司店、高級レストランなどに卸されています。
美味しい旬の時期は、漁期がおおむね12~4月ですので、これに準じて冬から春にかけてとなります。ただし、輸入物は、冷凍、活、解凍など含め1年中出回っています。

タイラギのおすすめの食べ方
貝全般に言えることですが、殻付きの場合は、必ず元気よく生きているものを選びましょう。砂地に生息していますので、むき身にしてから、必ず砂や汚れなどを綺麗に洗い流して下さい。貝柱だけで販売されている場合は色艶が良いものを選びましょう。身に透明感がなかったり、茶色っぽい色が付いている場合は鮮度が落ちている可能性が高くなりますので注意して下さい。
タイラギは貝柱とヒモ(外套膜)だけが食用となります。また、貝柱には硬い薄皮が付いていますので必ず取って下さい。また、ヒモはかなり歯応えがありますので、食べやすように小さ目に切っておくことをお勧めします。鮮度が良い場合は、ますはお刺身がお勧めですが、ホタテなどの貝柱と比べるとかなり硬いので、薄く切るか、隠し包丁などを入れることをお勧めします。加熱しても美味しいですが、火を通し過ぎるととても硬くなりますので、軽く通す程度にしておきまましょう。
※2枚貝は時期(おおむね春から夏)により自然毒(貝毒)を持つ場合がありますので、ご自分で採取される場合は、必ず各自治体の発表を確認し、該当する時期の採取は行わないで下さい(市場流通しているものは問題ありません)。また無許可の採取は罰せられる場合があります。

エゾバイ
エゾバイは、その名の通り北海道周辺に多く見られる貝です。市場ではイソツブと呼ばれることが多く、居酒屋の突き出しなどでよく見かける貝のひとつです。
肉食性で、臭いを頼りに魚などの死肉などを探して食べていますので、海のお掃除屋さんとも言えます。
この貝を目的とした漁の始まりは平成元年くらいからと歴史は浅く、理由も国産バイの水揚げが減少したことによる代替としての需要の高まりからです。ただし、漁が始まった当初は無計画な乱獲が行われたために、10年程度で一気に水揚げが減りましたが、今では稚貝の放流やサイズ制限などの資源保護が進められており、回復しつつあります。
エゾバイはほぼ1年中流通していますが、産卵期はおおむね5~9月ですので、美味しい旬の時期は冬から春にかけてと言われています。

エゾバイのおすすめの食べ方
貝全般に言えることですが、殻付きの場合は、必ず元気よく生きているものを選んで下さい。少し触っただけで、蓋がさっと閉まるくらいのものが目安です。エゾバイは小さいので可食部分が少ないのですが、太ると蓋をしても身が収まり切らなくなるようなものもいますので、出来るだけこのようなものを選ぶと良いでしょう。
エゾバイは大きくても5cm程度と小さいので、可食部分も少ないですが、加熱すれば内臓も全て食べられます。基本的に殻付きのまま調理して、食べる際に身を取り出すようになりますので、殻は綺麗に洗っておきましょう。
塩茹でや酒蒸しなどシンプルな料理であれば、エゾバイそのものの風味を味わうことが出来ますが、一番のお勧めは、醤油、酒、味醂、砂糖などで甘く煮付けた煮貝です。日持ちもしますし、お酒のあてはもちろん、ご飯のおかずとしても最適です。

バカガイ
バカガイとは可哀想な名前が付けられたものです。名前の由来には諸説あり、殻が薄くて割れやすい事から「破家貝」、移動するのが非常に早いことから「場替え貝」、バカのように沢山採れるから、バカのように半分口が開いているから、など様々な説があります。ただし、むき身にされたものは青柳(あおやぎ)と呼ばれ高級寿司ネタに、貝柱は小柱と呼ばれて、軍艦巻やかき揚げなどに用いられます。ちなみに青柳と言う名前は、この貝の集積場であった千葉県の青柳から来ていると言われています。
産地としては、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海などの内湾が主体です。しかし西日本ではあまり食べる習慣がないため、水揚げがあってもその場で廃棄されることもあるようです。また、潮干狩りなどでも沢山採れることがありますが、砂抜きなどの処理が難しいことなどから敬遠されることが多く、かなりの確率でリリースされているようです。
美味しい旬の時期は、産卵期が5~7月ですので、春と言うことになります。

バカガイのおすすめの食べ方
貝全般に言えることですが、殻付きの場合は、必ず元気よく生きているものを選びましょう。また、大き目のものは、手にもってズッシリと重みを感じるものでなければなりません。
バカガイは砂を大量に噛んでいることがありますが、アサリのように塩水に一度漬けておくだけでは処理出来ません。砂がなくなるまで何度も水を入替した後、むき身にしてから再度洗う下処理が必要となります。小さなものであっても、砂噛みのリスクを避けるため、面倒でも必ずむき身にしてから調理しましょう。ただ、どうしても面倒ならば、ボイルしたむき身や貝柱に処理されたものを購入しても良いですが、処理されたものは殻付きに比べかなり割高になりますので、色艶が良く、肉厚なものを慎重に選んで下さい。
食べ方としては、ボイルしたむき身はお刺身、小柱はお刺身か、かき揚げがポピュラーです。シーズン中の殻付きはかなりお安いので、手間さえ惜しまなかれば、焼物、煮物、炒め物など様々な料理を楽しむことも出来ます。
※2枚貝は時期(おおむね春から夏)により自然毒(貝毒)を持つ場合がありますので、ご自分で採取される場合は、必ず各自治体の発表を確認し、該当する時期の採取は行わないで下さい(市場流通しているものは問題ありません)。また無許可の採取は罰せられる場合があります。

マテガイ
マテガイは細かく分けると、マテガイ、オオマテガイ、アカマテガイ、エゾマテガイなどがありますが、全てマテガイとして流通しており、区別されることはありません。
その中でもマテガイは、潮干狩りなどでも採りやすいため、一番馴染みがあると言っても良いでしょう。ただし、その採り方は独特で、マテガイが潜っているところに開いている穴を探し、そこに塩を注ぐと、マテガイが驚いたように飛び出すので、それを素早く掴むと言ったものです。
昔は身近に見られた貝だったのですが、近年は様々な要因により生息場所が少なくなっており、産地としては長崎県や熊本県の有明海沿岸、愛知県三河湾、、三重県伊勢湾、山口県の瀬戸内海沿岸などに限られます。加えて、マテガイの仲間は輸送に弱いため、ほとんど産地で消費されてしまい、消費地にはほぼ出回りませんが、殻が薄く歩留まりがいいこともあってか、産地市場でも高めの値が付くことが多いようです。
水揚げが増えるのは、産地によって多少ずれていますが、全体に秋から春に増える傾向が高いため、この時期を旬として良いのではないでしょうか。

マテガイのおすすめの食べ方
マテガイは細かく分けると、マテガイ、オオマテガイ、アカマテガイ、エゾマテガイなどがありますが、全てマテガイとして流通しており、区別されることはありません。
その中でもマテガイは、潮干狩りなどでも採りやすいため、一番馴染みがあると言っても良いでしょう。ただし、その採り方は独特で、マテガイが潜っているところに開いている穴を探し、そこに塩を注ぐと、マテガイが驚いたように飛び出すので、それを素早く掴むと言ったものです。
昔は身近に見られた貝だったのですが、近年は様々な要因により生息場所が少なくなっており、産地としては長崎県や熊本県の有明海沿岸、愛知県三河湾、、三重県伊勢湾、山口県の瀬戸内海沿岸などに限られます。加えて、マテガイの仲間は輸送に弱いため、ほとんど産地で消費されてしまい、消費地にはほぼ出回りませんが、殻が薄く歩留まりがいいこともあってか、産地市場でも高めの値が付くことが多いようです。
水揚げが増えるのは、産地によって多少ずれていますが、全体に秋から春に増える傾向が高いため、この時期を旬として良いのではないでしょうか。

ミルクイ
ミルクイのミルとは海中に生えるミル科の緑藻類のことで、ミルクイの長い水管の先端の固い箇所にこれが生えることが多く、この貝がこの海藻を食べているように見えるのが名前の由来とされています。一般的にはミルガイと呼ばれており、大型で食味が良いことに加え、採れる数も本当に少ないことから、超高級品となっています。このため、よく似たナミガイが代用品として利用されることが多くなっていますが、ナミガイは殻が白い事からシロミルと呼ばれるのに対し、ミルクイは見た目が黒いこともあるため、クロミルと呼ばれたり、本物のミルクイの意でホンミルと呼ばれたりして区別されています。
大きな特徴は発達した水管で、太く大きいため殻を閉じても中に収納さすることが出来ません。また、水管は黒い皮に包まれ、先端部には硬い殻状の皮がありますので、見た目は正直良いとは言えません。
主な産地としては、三河湾や東京湾などですが、前述した通り、その量はわずかです。近年は韓国から活で輸入されることもあれば、近縁種のアメリカナミガイの輸入も増えています。
ミルクイの産卵期は産地や個体で大きな幅があり、いつとは言い難いのですが、おおむね春と秋の2回とされており、夏になると水揚げが減る傾向にあります。したがって、美味しい旬の時期は、冬から春までと見た方が良いでしょう。

ミルクイのおすすめの食べ方
貝全般に言えることですが、殻付きの場合は、必ず元気よく生きているものを選びましょう。水管に触れた際に、素早く反応するものでなければなりません。最も美味しい部分は水管なので、この箇所が太く大きいものを選びます。
ミルクイは基本的には殻と水管の表皮以外全て食べることが出来ます。お刺身やお寿司に使うのは、水管、貝柱、ヒモ(外套膜)、ミル舌と呼ばれる脚です。水管はさっと熱湯を当てて表面の黒い皮を剥いて使います。お高い貝なので、勇気がいりますが、旨味の強い貝ですので、煮物、焼物、揚物などにしても美味しく頂くことが出来ます。
※2枚貝は時期(おおむね春から夏)により自然毒(貝毒)を持つ場合がありますので、ご自分で採取される場合は、必ず各自治体の発表を確認し、該当する時期の採取は行わないで下さい(市場流通しているものは問題ありません)。また無許可の採取は罰せられる場合があります。

アオサ(総称)
アオサは、アオサ目アオサ属に属する海藻の総称ですが、食用として主に流通しているのはアナアオサと言う種類になります。見た目が同じアオサ目のアオノリに似ているため、同じものだと思われている方も多いようですが、アオサは海に生息しているのに対して、アオノリは湖や汽水域が生息場所となります。また、いずれも乾燥して流通することが多いのですが、アオサは栽培が盛んなこともあってかアオノリと比べると安価です。ちなみに、お好み焼きなどに振りかけるアオノリはアナアオサを乾燥させ粉末状にしたものであって、アオノリではありません。
主な産地は愛知県と三重県で、ほぼ栽培です。九州や四国でも見られますが、自生しているものを収穫することが多いので、生産量は多くありません。このうち特に多いのは愛知県三河湾で、アオサを粉末にした「あおさ粉」の約70%が三河湾のものと言われています。
乾燥したものは1年中流通していますが、摘み取りは1~5月で、産地によっては、これを摘み取る様子が春の風物詩になっています。
アオサは乾物での流通が基本となりますが、加工したてのものはとても風味が良いので、ぜひこの時期に味わって頂きたいものです。

アオサのおすすめの食べ方
生が手に入った場合は、砂やゴミなどが付着している確率が高いので、良く洗って下さい。アオサは香りが味わいのひとつですが、生の場合は香りが強く、鼻に付くこともありますので、調理する前に軽く茹でて香りを抑えておくと良いでしょう。
乾物の場合は、そのまま使う方法と、水で戻す方法があります。海苔のよう使う場合は、そのまま冷奴や納豆などにふりかけても良いですが、軽く炙るとで香ばしさが増します。水で戻したものは、味噌汁、天ぷらが定番ですが、卵焼き、お好み焼き、チヂミなどに入れたりするのもお勧めです。
※無許可の採取は罰せられる場合があります。

ノリ
日本人の食生活に最も欠かせない海草は海苔(のり)ではないでしょうか。いつ頃から食べられ始めたかについては定かではありませんが、701年に制定された大宝律令には税制の対象として紫海苔の記載がみられることから、かなり昔から食用としていたことは間違いなさそうです。
ノリと名前が付く海草には、スサビノリ、アサクサノリ、アマノリ、アオサ、アオノリなどがありますが、普通ノリと言うと、スサビノリを指します。アサクサノリの生産が盛んだった頃もありましたが、環境に左右されやすい種であるため、現在ではほとんど見られなくなっています。
ノリは夏から秋にかけて、河口近くの海にノリヒビ(養殖海苔を付着し成長させる道具)を設置し、11月下旬頃から2月頃まで続きます。11月頃に収穫されたものを「新海苔」と呼びますが、流通するのは乾燥した後となりますので、出回りは12月からとなります。
乾物での流通が圧倒的に多いため、旬を感じにくい食材のひとつですが、出来立ての方が風味が良いので、特にこの時期は出来るだけ新しいものを選んだほうが良いでしょう。

ノリのおすすめの食べ方
品質の良いノリは、色が黒く濃く、光沢があり、焼くと綺麗な緑色になり、良い香りが立ちますが、時間の経過とともにその味わいや香りは落ちてきますので、この時期に必ず味わっておくべきものです。新海苔の場合は、余計なことをぜず軽く炙って香りを立てたものをそのままか、軽く醤油を付けたものでご飯を食べるのが最も良い食べ方でしょう。
雑炊や佃煮にしても美味しいですが、香りを楽しむ料理ではないので、この類は収穫が終了してからのもので十分間に合います。
※無許可の採取は罰せられる場合があります。

ワカメ
ワカメは、1年で一生を終える1年草です。秋に受精したものが、冬から春にかけて一気に成長し、この成長期が収穫時期となります。ただし、ワカメは自己消費のスピードがすさまじく、鮮度維持が難しいため、生鮮は産地であってもあまり見かけません。ですので、収穫後すぐにボイルし、そのまま乾燥するか、塩蔵処理して水抜きをした後に、加工原料として保管するかのいずれかになります。塩蔵処理したものは、その後に選別・計量を経て、塩蔵品として出荷されます。塩蔵にすると風味が失われそうですが、ワカメの場合はこれが最も良い保存方法とされており、風味も色合いもかなり残ります。
ワカメは栽培が主体で、沖縄県や九州南部を除く 日本各地で広く生産されていますが、生産量が多いのは宮城県、岩手県、兵庫県(淡路島南端)、徳島県です。 宮城県と岩手県のわかめは三陸わかめ 、兵庫県と徳島県のわかめは鳴門わかめとそれぞれブランド化されています。また、中国や韓国などからの輸入物も多く、安価で流通していますが、味わいや香りはやはり国産が上です。
鳴門わかめは、その名の通り鳴門海峡で育ったワカメで、徳島県と兵庫県淡路島の特産品です。葉は薄いのですが、綺麗な緑色でシャキッとした歯応えを楽しめるのが特徴で、1~4月に収穫されます。三陸わかめは、全国の収穫量のおよそ90%を占めていると言われている大産地で、特徴は肉厚で弾力のある食感で、収穫は冬から初夏にかけて行われます。もうひとつ南方型ワカメと呼ばれるものがあります。こちらは比較的マイナーな存在ですが、主に本州中部より南の日本海側で採れたワカメのことで、栽培ではない場合が多く、小ぶりで、茎も短いのが特徴ですが、ワカメの香と言う点では一番強いかも知れません。こちらの収穫時期は冬から春にかけてです。
塩蔵や乾物での流通が基本ですので、旬を感じにくい食材のひとつですが、出来立ての方が風味が良いので、特にこの時期は出来るだけ新しいものを選んだほうが良いでしょう。

ワカメのおすすめの食べ方
生のワカメは手に入りにくいですが、もし見かけたら、艶があり、綺麗な茶色で、軽い磯の香がするものが良いでしょう。
塩蔵のは袋に入っていることが多いので、確認しにくいですが、葉が濃い緑色をしたものを選んで下さい。また、塩蔵の場合は、塩込みの重量で表示されていることもありますので、内容量の確認も必要です。また、茎付きと茎なしがありますので、調理によって選んで下さい。
乾燥ワカメは、しっかり乾燥していることはもちろんですが、色艶が良いものを選びましょう。乾燥したものは、板状のものから、細かくカットしたものまで色々ありますので、調理によって選ぶと良いでしょう。
お勧めの料理はあくまで参考となりますが、鳴門海峡のものは歯応えと綺麗な緑色が特徴ですが、加熱してしまうと色が褪せて、食感も失われますので、和え物やサラダなど、いわゆる生食に向きます。三陸のものは肉厚ですので、加熱しても風味や食感が失われることが少ないので、汁物や煮物などに向きます。
収穫時期にはメカブや茎なども出回ります。メカブは細かく叩くことでネバネバになりますので、ご飯にかけたり、和え物にするなどして楽しむことが出来ます。茎は柔らかいものが大前提になりますが、炒め物や佃煮にすると美味しく頂けます。太くて硬い茎は歯応えがあり過ぎるので、圧力鍋などでしっかり加熱しないといけません。
また、収穫時期は塩蔵処理したものを軽く水戻しした「なんちゃって生ワカメ」も出回ります。生だと信じて調理すると、とんでもなく塩辛い場合がありますので、注意して下さい。
※無許可の採取は罰せられる場合があります。

エゾバフンウニ
エゾバフンウニは、生殖巣が鮮やかなオレンジ色をしていることからアカウニとも呼ばれています。ウニの中では最も収穫量が多いとされていますが、風味や味の良さから高級品として扱われています。中でも利尻や羅臼で獲れるものは、昆布を食べているため、最も風味が良いとされ、高値で取引されています。
名前に蝦夷と付くだけあって、水揚げのほとんどは北海道ですが、東北地方でも少ないながら採れています。また、はロシア、韓国、中国にも生息しており、板ウニなどに加工されたものが輸入されていますが、味わいは国産にはかなわないと言われています。
国内の産地では、資源保護のため各地で種苗放流が行われており、厳格な漁期も定められています。主なところでは、渡島が12~9月、石狩と後志が5~8月、宗谷が4~9月、根室が12~6月となっています。10~11月以外漁期と言うことになりますが、生殖巣が最も充実するのは6~8月と言われています。

エゾバフンウニのおすすめの食べ方
殻付きのまま販売されていることもありますが、見た目や持った感じで良し悪しを判断するのが難しいので、販売店の方に良く吟味して頂いた方が良いでしょう。
新鮮な殻付きは美味しいのですが、生殖巣を取り出すのはかなり手間ですので、当たり外れが少なく無難なのは板ウニや塩水ウニです。
エゾバフンウニは生のまま食べるのは一番美味しいとされています。お刺身はもちろん、お寿司や丼などご飯との相性も抜群です。
※無許可の採取は禁止されています。

バフンウニ
バフンウニは殻径が5cm程度の小型のウニで、殻は全体的に緑っぽいのが特徴です。
味が良く、人気はあるものの収穫量が少なく、殻も身も小さくて手間がかかることもあり、生鮮は産地周辺でほとんど消費されてしまいます。生鮮で消費地に出回っているバフンウニと呼ばれるもののほとんどはエゾバフンウニで、まず本種ではありません。本種は生鮮より加工品の原料として有名で、日本三大珍味の「越前うに」の原料にもなっています。
北海道を除く日本全土で生息が確認出来ますが、産地としては突出したところはありません。一番美味しいとされる時期は産地によってずれがあり、西日本で1~4月頃、北陸地方などでは夏頃とされているようです。

バフンウニのおすすめの食べ方
バフンウニが殻付きのまま流通することはほとんどありませんが、他のウニと同様に、見た目や持った感じだけで良し悪しを判断するのは難しいので、販売店の方に良く吟味して頂いた方が良いでしょう。新鮮な殻付きは美味しいのですが、特にこのウニは小さく、生殖巣を取り出すのは相当手間ですので、お刺身にされる場合は、板ウニなどを購入された方が無難でしょう。生鮮のバフンウニは産地でないとなかなかお目にかかれませんが、機会があれば一度は味わっておいて欲しいものです。
練ウニなどの加工品は1年中出回っていますので、いつでもお召し上がり頂くことは出来ますが、加工したばかりのものが良いと言う人もいれば、製造から日にちがある程度経って塩味が馴染んだものの方が良いと言う人もいますので、ご自分でお確かめください。
※無許可の採取は禁止されています。

ナマコ(総称)
日本で食用とされているナマコは、アオナマコ、アカナマコ、クロナマコの3種ですが、長年、学術上の分類は全て同じマナマコとされていました。生息場所や外見もかなり異なるため、研究が進められた結果、アオナマコとクロナマコはほぼ同じで、アカナマコは別種との結果が出ました。
国内の評価は、アカ→アオ→クロとなっており、アカナマコが最も高値で取引されています、一方クロナマコは生での食感が悪いため、昔は値段も付かず厄介者扱いされていましたが、乾燥することで高級中華食材となることがわかったため、今では主に輸出用として加工されることが多くなりました。
ナマコの水揚げ統計はひとまとめになっていますので、詳細はわかりませんが、産地として最も多いのは北海道で全体の約3割強を占めています。次いで、青森県、山口県、兵庫県、大分県と続きます。ちなみに、アカナマコは主に西日本、アオナマコトクロナマコは全国に分布しているものの、北日本が多いとされています。
漁期は地域により若干ずれがありますが、ナマコは海水温が高いと休眠し、海水温が低くなると活発に動き出しますので、11月頃から漁が始まり、春手前で終了と言うところが多いいですので、美味しい旬の時期は真冬と言うことになります。

ナマコのおすすめの食べ方
ナマコは丸のまま、切ナマコ、黄って味付けしたもののの流通があります。切って味付けしたものが一番手軽ですが、この類は冷凍しているものが多いため、ナマコ特有のコリコリとした食感が失われていることが多いため、あまりお勧めは出来ません。歯応えで言うと、一番良いのはやはり生きているものです。目安としては、触った時にすぐにぎゅっと縮むもので、突起がはっきりしているものを選ぶと良いでしょう。触っても動きがなく、だらッとしているものや、突起がなく表面が解けているようなもの、容器の水が濁っているようなものは、切ナマコも含めては避けた方が良いです。
生のナマコは加熱すると、とんでもなく縮んでしまい、やたら硬くなるだけですので、一番のお勧めは酢の物です。また、家庭で作ることは困難なんですが、ナマコの内臓を加工した珍味はとても有名です。「このわた」は内臓の塩辛で、日本三大珍味のひとつになっています。卵巣に塩をして干したものは「クチコ」と呼ばれており、こちらも高級珍味です。
※無許可の採取は禁止されています。



 0
0














